新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、参加人数が5,000人超かつ収容率50%超(緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域においては5,000人超)のイベントの開催を県内で計画されているイベント主催者におかれましては、下記により県に「感染防止安全計画」(以下「安全計画」(エクセル:173KB))を策定し、県に提出していただきますようお願いいたします。
「感染防止安全計画」策定の対象とならないイベントにつきましては、下記によりイベント開催時のチェックリスト(以下「チェックリスト」)(エクセル:85KB)を作成の上、HP等で公表していただきますようお願いいたします。(この場合、チェックリストの県への提出は原則不要です。)
◎下記のとおり「イベント開催における感染防止安全計画等の作成の手引き(別紙1-3)」を作成しましたので、本手引きに基づき作成してください。
(別紙1)イベント開催における感染防止安全計画等の作成の手引き(PDF:139KB)
(別紙2)感染防止安全計画について(PDF:211KB)
(別紙3)イベント開催時のチェックリストについて(PDF:194KB)
◎なお、よくある質問(FAQ)(PDF:671KB)についてまとめましたので、お問合せ前に御確認ください。
【参考資料】:第27回基本的対処方針分科会_参考資料1(マスク着用の考え方)(PDF:712KB)
【参考ページ】:マスク着用についての目安(新型コロナウイルス感染症⾧野県対策本部)
Ⅰ.開催基準について
1.令和4年3月7日以降のイベント開催基準
人数上限は収容定員まで、収容率の上限を100%とする(大声なしの担保が前提)
人数上限5,000人又は収容定員の50%いずれか大きい方かつ収容率の上限を50%(大声での歓声、声援等が想定される場合等。以下、「大声あり※」という。又は100%(大声なし)とする。
(※)「大声」を「観客等が、(ア)通常よりも大きな声量で、(イ)反復・継続的に声を発すること」と定義し、これを積極的に推奨する又は必要な施策を十分に施さないイベントを「大声あり」に該当するものとする。
イベント開催等における必要な感染防止策(PDF:524KB)
2.業種別ガイドライン
Ⅱ.安全計画について
1.安全計画策定の対象となるイベント
- 参加人数が5,000人超かつ収容率50%超のイベント(※1、2、3)
(※1)長野県が緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された場合においては5,000人超のイベントが対象とな
ります。
(※2)参加者を事前に把握できない場合は、イベントと主催者等が想定する参加予定人数が5,000人超の時、収容定員が設定さ
れていない場合は、人と人とが触れ合わない程度の間隔で開催したい時、安全計画策定の対象となります。
(※3)「イベント」には緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域における遊園地等の集客施設を含み、「イベント主催
者等」には当該施設の管理者を含みます。
2.安全計画策定の対象期間
令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、安全計画の策定は不要です。
ただし、人数上限を拡大する場合は改めて安全計画の策定が必要です。
3.安全計画策定の対象者
4.安全計画策定の流れ
↓
- イベントの開催、感染防止対策の実施状況を確認できる要領やチラシ、パンフレットを添付の上、県に提出してください。(イベント開催の2週間前までに)
↓
- 内容をチェックして確認事項、お願い事項等について、ご連絡させていただきます。
↓
- 当日は、安全計画、ガイドライン等に沿って、感染防止対策の徹底をお願いします。
↓
5.留意事項
- 安全計画の提出後、計画が変更となった場合には、変更した安全計画を速やかに提出してください。
- 一定期間に反復的に同一施設を使用して同様のイベントを実施する場合には、一括して安全計画を策定し、提出することが可能です。
(関連情報)長野県ワクチン・検査パッケージ定着促進等事業に係る無料検査実施事業者を募集します。
Ⅲ.チェックリストについて
1.チェックリスト作成(公開)の対象となるイベント
- 安全計画を策定しない全てのイベントが対象となります。
2.チェックリスト作成(公開)の対象期間
令和3年11月24日までに従前の事前相談が済んでいるイベントは、チェックリストの作成(公開)は原則不要です。
3.チェックリスト作成(公開)の対象者
4.チェックリスト作成(公開)の流れ
↓
- 該当イベントのホームページ又は会場にて作成したチェックリストを公開してください。(県への提出は必要ありません。)
↓
- 当日は、作成したチェックリストの感染対策を徹底してください。
↓
- イベント終了後、終了日から1年間、チェックリストを保管してください。
※問題発生時(クラスター発生、基本的対策の不徹底等)は「イベント結果報告書」(エクセル:19KB)を県へ提出してください。
Ⅳ.安全計画の提出方法等
1.提出先
長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室
2.提出書類
【安全計画を策定する場合】
【チェックリストを作成(公開)する場合】
※チェックリストは事前に県へ提出する必要はありません。
3.提出方法
上記の書類を次の下記のいずれかの方法でお送りいただくようお願いします。(安全計画についてはイベント開催の2週間前を目途に、送付してください。)
送信先メールアドレス:corona-taisaku@pref.nagano.lg.jp
※メールの件名は「イベント安全計画」または「イベント結果報告」としてください
送信先FAX番号:026-233-4332
宛先:380-8570(専用郵便番号のため住所記載不要)
長野県危機管理部消防課新型コロナウイルス感染症対策室
イベント開催事前相談担当者 宛
4.その他
- 従前行っていた全国的な人の移動を伴う又は収容人数が1,000人を超えるイベントに係る事前相談は令和3年11月24日の受付をもって終了します。
- 提出いただいた書類の内容を確認した上、1週間後を目途にメール又は電話によりご回答させていただきます。
- 書類の内容を確認するにあたり、メール又は電話にて感染防止対策等についてご質問させていただく場合があります。
- イベントにおいて集団的な感染が判明した場合は、開催状況についてご質問させていただきますので、ご承知おき願います。
【参考】長野県の対応方針、内閣官房事務連絡



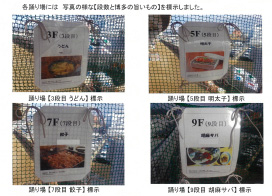


 (別添)令和4年度全国労働衛生週間 実施要綱[PDF形式:174KB]
(別添)令和4年度全国労働衛生週間 実施要綱[PDF形式:174KB]