|
特集 2005年版 中小企業白書の概要
第1章 経済構造の変化と中小企業の経営革新
経済構造の変化と中小企業
1.経済再活性化の動きと中小企業
2004年5月に経済産業省が策定した「新産業創造戦略」では、「国際競争に勝ち抜く高付加価値型の先端産業群」、「健康福祉や環境など社会ニーズの広がりに対応した産業群(サービス等)」、「地域再生に貢献する産業群」を三本柱として政策資源を投入していくこととしているが、このような我が国の経済構造、産業構造の活性化に向けた動きが結実するには、経済の大部分を占める中小企業における相当な変化が前提になる。経済構造全体の変化と整合的な方向で、個別中小企業レベルでの経営革新や創業といったリスクに積極的に挑戦する活動を促進し、総体としての我が国経済の再活性化につなげていくことが必要である(第1図)。
第1図
新産業創造戦略と中小企業の経営革新との関連図
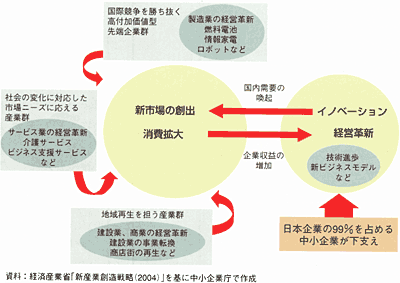
2.中小製造業における取引環境の変化
(1)経済のグローバル化による中小製造業への影響

中小製造業がグローバル化の影響を受けるのは、大きく分けて2つの要素がある。1つは取引先の海外移転、1つは海外製品との競合である。(社)中小企業研究所「製造業販売活動実態調査」により、中小製造業を対象に1999年以降の上記2つの影響をみたところ、「取引先の海外移転等」を34.0%が経験し、また「海外製品との競合による販売量の減少」を51.6%が経験し、特に中国を中心とした東アジア諸国の流入品の影響を受けている状況にある。
一方、海外市場という観点でみた場合、このようなグローバル化は製造業にとって企業活動の範囲を大きく変えている。実際、第2図にみるように、輸出、輸入、海外直接投資を行う中小製造業が増えており、日本の中の中小企業ではなく、世界の中の中小企業として、活躍する中小製造業が増加している。
今後、世界各国の経済は人口動態の違い等から東アジア諸国等が成長の中心になると予想され、例えば自動車業界の販売・生産予測をみても日本以外のアジア市場の成長率が大きくなっている。また、近年、東アジアを始めとする諸国との間でFTA(自由貿易協定)を締結する動きがみられ、グローバル化は一層加速していくと見込まれる。
第2図
大企業・中小企業別海外展開の状況(製造業)
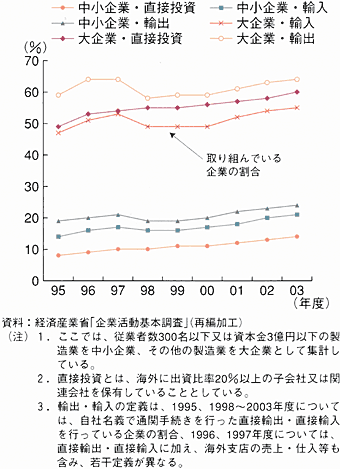
(2)下請構造の変化と新たな形態の企業間協力の進展
グローバル化の進展、不況の長期化などで、こうした下請取引環境は変化しつつある。大企業の生産拠点の移転や、大企業自身の業績悪化等により、「系列」を維持していくメリットや体力が失われており、下請企業からみても下請であるメリットは失われてきたのである。実際、1981年には65・5%を超えていた下請企業の割合は、1998年に47・9%と減少しており、さらに、現在の下請取引の割合が高い企業も、下請受注の比率の低下を望んでいる企業が多く、今後は従来以上に下請企業が減少することが予想される(第3図)。
これまで日本を支えてきた下請企業は徐々に減少していく傾向にあるが、こうしたことは自ら商品を企画し、自ら販売活動を行う、自立した中小企業が増加していることを意味している。このように自立の程度を高めた状況で企業が生き残るためには、自ら販路を開拓しつつ、利益を上げなければならない。利益を上げるには1つはコストを抑える「低コスト化」、1つは付加価値を上げる「高付加価値化」とおおむね2通りの方策があり、中小製造業においては、これらの活動に取り組んでいく必要がある。
特に、相対的に経営資源の乏しい中小企業においては、自社で企画~生産~販売まで完結できる企業は少なく、近年では大学、研究機関等、販売先、仕入・外注先等の外部企業又は機関との企業間連携により、不足する経営資源を補っていくことが重要となっている。
第3図
下請構造の変化
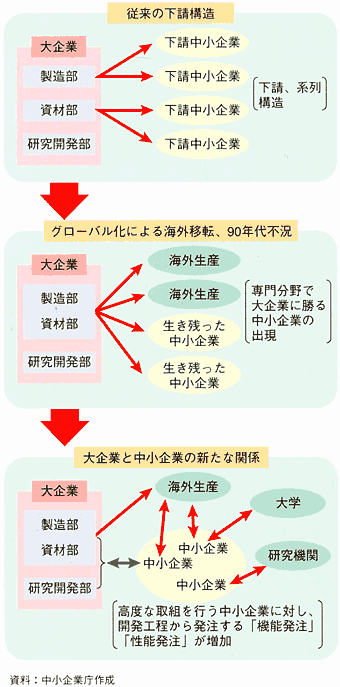
3.サービス経済化の進展等
(1)サービス経済化と製造業のサービス化

わが国の企業の業種構成をみると、サービス業の割合が増加しているが、その内訳は主に情報サービス業、専門サービス業等で増加している。
サービス経済化の動きがみられるのは、サービス業の増加だけにみられるものではない。製造業において人材ベースでみると企画・開発に携わる研究開発部門の従業員の増加(第4図)や、金額ベースでみると製造業への中間投入比率においてサービスの割合が増加していること等のソフトな経営資源への投資ウェイトが高まっている。特に、小規模製造業では、一般的な製造業と業態が異なり研究開発や試作品開発に特化する「研究開発型企業」や、工場、生産設備をもたず、生産工程はすべて外注化している「ファブレス」、流通ルートを介さず自社で製造から小売まで一貫して行う「製造小売」など新しい業態への多様化もみられる。
また、製造業ではこうしたソフトな経営資源において自社に競争力がないのであれば、外注化(アウトソーシング)により調達する傾向もみられる。第5図によると、大企業、中小企業を問わず、研究開発関連やデザイン・商品企画関連といったソフト事業を外部委託している企業が増加している。つまり、製造業も「モノ」だけを生産することだけに注力するのではなく、デザイン・コンセプト・付加サービス等のソフト要素を付加することによる差別化、高付加価値化を図っているのである。
第4図
製造業における研究開発人員の割合
~大企業、中小企業共に、研究開発関連の従業者の割合が増加~
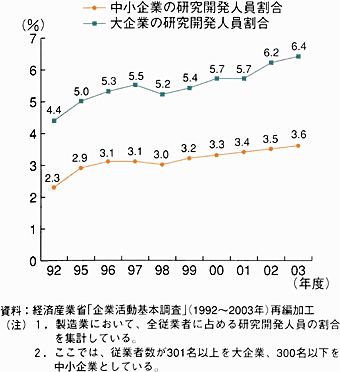
第5図
製造業の研究開発、デザイン・商品企画の外部委託状況
~近年、デザイン・商品企画、研究開発関連の外部委託を行う企業が増加している~
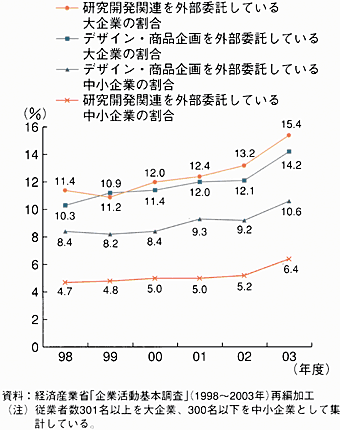

「扇町インキュベーションプラザ(通称:メビック扇町)」(大阪府)は、2003年に創設されたインキュベーション施設である。従来型のインキュベーション施設に多い技術系研究施設とは異なり、映像・広告・デザイン関連などのコンテンツ系やソフトウエア・インターネット関連等のIT(情報処理)産業の企業、いわば第4次産業・第5次産業を対象とした施設である。
大阪には、大阪市や東大阪市を中心に中小製造業の産業集積があり、同地域には高性能、高効率、低コストという面で非常に優れた企業が多いものの、こうした高性能製品を「販売に結びつける」という面で苦戦している企業も多い。一方で、当施設は情報系、デザイン系企業が集積している大阪市の中心に位置しており、クリエーターやデザイナーの創業支援や、「ものづくり」等の既存産業と「クリエーター、デザイナー」とのマッチング支援を行っている。
【製造業とデザイナーの経営者の違い】
当施設は開業後約2年経過したが、製造業とデザイナーのコラボレーションは「経営者の属性」という面で難航することが多い。製造業の経営者は技術系の出身が多いせいか、いかに高性能か、低コストかという機能的、物理的な視点での眼力には長けているものの、デザインを付加するという意識は非常に低い。むしろ、「デザインにコストをかける必要性はない」と考える経営者も多い。一方、クリエイターやデザイナーはコスト意識、時間制約といった意識は低く、経営者というよりは芸術家に近いという属性がある。
【ものづくり+デザインの融合によるビジネスの広がり】
「ものづくり」と「デザイナー」の経営者は元々異質の世界で育ってきたことから、お互いの感性を理解することは難しく、ビジネスとして結びつきにくい面があるが、同施設を利用することにより、うまくマッチングして成功するケースも増えてきている。一例を挙げれば、「長年繊維生地を作っていたメーカーと家具デザイナーとのコラボレーションにより高感性のインテリア製品(応接椅子)が開発され、新たな販路を開拓し、付加価値を高めた」企業等もある。
このように「ものづくり」側からみると、高性能・低コストを追求した製品からもう一歩踏み込んだ商品にできる創意工夫、いわば「見せる」術を持つこと、一方で「デザイナー」側からみると、芸術家から脱皮し、その「芸術性」をビジネスに持ち込むことでイノベーションが生まれ、新しいビジネスが創造されるのである。 |
4.経済構造の変化と中小企業経営
(1)既存企業の「経営革新(イノベーション)」の重要性

近年の経済環境の変化の中で、中小企業はどのように活動してきたのであろうか。バブル期以降の10年をみると、開業数が廃業数を下回り、従来から存在する既存企業の経営革新(イノベーション)の必要性は増している。日本経済の再活性化のためには、企業に創業期~成長期~成熟期~衰退期というライフサイクルというものがあるならば、成長期あるいは成熟期でこそ経営革新への取組を活発化し、企業成長を実現することが重要な課題となる。
実際、長期にわたって存続する企業であっても、同じ事業内容で続くわけではなく、常に変化する市場等の状況に応じて、企業規模や業種・業態等を変化させる、いわば自らの経営のあり方を適合させる動きがみられる。
例えば、市場への適合を「企業規模の変化」という観点でみてみよう。総務省「事業所・企業統計調査」により5年間(1996~2001年)での企業規模の変化をみると、規模が大きい企業ほど、拡大する企業と縮小する企業の割合が増え、相対的には縮小した割合が高い。また、企業の質という面では中小企業金融公庫「経営環境実態調査」により、10年間の主力事業の内容の変化をみると、企業規模の大きさに関わらず、「約10年前と業種・業態が異なる」が1割程度、「約10年前と同じ業種・業態だが、提供する商品が異なる」が4割程度となっている(第6図)。
規模の変化、企業の質的な変化がみられる背景には、経営者のマインドの他、市場動向、競争環境の状況等が非常に強く影響していることが挙げられる。つまり、5~10年という時間を経ると市場環境は大きく変化し、企業規模という外見でわかる企業の形も、業種・業態、取扱商品の内容といった企業の質という面でも、企業は大きく変化しているのである。
第6図
10年間の主力事業の内容変化
~10年間の間に約半数の企業は主力事業を変更しており、
約1割は業種・業態そのものを変えている~
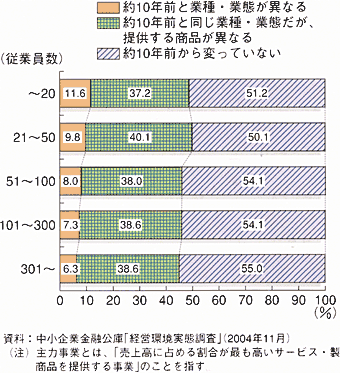
| 事例2 経営者のリーダーシップにより、生まれ変わった企業 |

A社(兵庫県、従業員18名)は、醤油メーカーであったが、食生活の変化の影響をうけて1980年代頃から醤油需要の伸び悩みにより営業不振に陥り、倒産の危機に瀕した。醤油事業そのものの事業継続は難しくなったが、醸造で培った発酵技術自体は別の分野に転換することで次の時代の産業につなげていくことができると考え、1996年に醤油事業から撤退し、醤油醸造場時代に培った微生物の発酵技術を利用して、環境浄化事業に取り組んでいる。
【時代の変化を乗り越えるには、経営者のリーダーシップが必要】
醤油事業は、慶応年間から続いた伝統ある醤油蔵であるが、醤油や酒などの醸造業は、代々受け継がれるいわゆる「家業」としての色彩が非常に濃い。長い歴史のなかで、地域産業の担い手として地域経済に果たしてきた役割も大きく、それがプライドでもあったのだが、反面、かえって廃業しにくい面があった。特に醤油事業時代の従業員が持っていた技術は醤油醸造として技術は優れているものの、A社が取り組もうとした新しい分野に必要な技術に、ついてこれなくなった者も多かった。
しかしながら、醤油醸造を行うわけではなく、醤油醸造で培った「発酵技術」を応用した新製品の開発を行うことが大命題であったので、醤油醸造の視野しか持たない従業員については、残念ながら引き継がないものとして考えるほかなかった。特に、次の事業展開を行うときの重要なポイントは、過去から引き継ぐべき技術・ノウハウ・従業員、のれん等資産と、引き継がないものとの区別を明確にすることである。過去から積み上げてきたものを捨てることは、経営者にとって苦渋の選択ではあるが、逆にその場面でA社の社長は強い意志を持ち、リーダーシップをとって行ってきたことにより、現在の事業を成長させることができたのである。
【大きく変貌したA社の姿】
その後事業は大きく変り、現在は「微生物培養」、「畜産糞尿処理システム」、「含油廃水処理システム」、「汚泥減量化装置」、「Nプラスチック(生分解性プラスチック)」等を行っているが、すべての事業に微生物を利用した発酵技術が応用されている。こうした発酵技術の研究・開発、それを利用した製品の開発は、大学や研究機関に間借りするかたちで設けている6ヶ所の研究開発拠点で行っている。
A社はこうした開発過程で生まれる技術を全て特許化している。技術情報の秘匿による模倣の防止よりも、特許化することで自社のロイヤリティを保護しつつ社会に技術情報を開示し、より多くの人々に活用してほしいと願ってのことである。A社の姿は醤油醸造時代の地域産業の担い手という存在から、特許化により技術を社会還元する存在へと大きく変貌したのである。 |
高い創造性を産み出す新製品開発と事業連携
1.中小製造業の研究開発・新製品開発への取組
(1)中小企業の研究開発の独自性
中小企業と大企業でこれらの研究開発の内容を比較すると、大企業はこうした基礎研究―応用研究―実用化研究など一連の研究を自前で行う割合が高いのに対し、中小企業では実用化研究に特化した研究を行う割合が高い(第7図)。
また、研究開発の質も企業規模別に違いがみられる。大企業が行う研究開発は比較的需要が大きい市場を目指して行われることから、先行した研究開発を行ったとしても、競合企業が追随してくる。つまり、大企業は同質的行動を取るのに対し、中小企業の研究開発は、誰もが行わないような「独自性」を追求したものが多い。実際、企業規模別に研究開発の内容と競合他社との関係をみると、規模が大きい企業は、技術的に先行していても他社の追随を受けている企業又は自社が競合他社に対して遅れをとっている企業の割合が高いのに対し、規模が小さい企業ほど「競合他社では全く行われていない研究開発をしていることが多い」割合が高い。こうした研究開発の質の違いが製品開発にも影響し、中小企業は業界初といったような今までの市場にない新製品を多く産み出す結果となって現れているのである(第8図)。
第7図
企業規模別研究開発の内容
~中小企業の多くは、実用化研究に特化した研究開発を行っている~
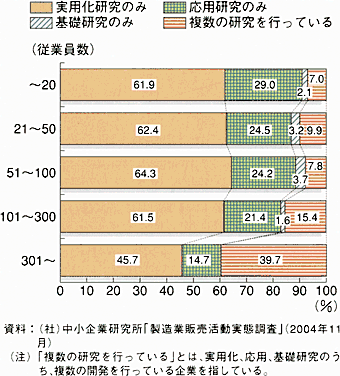
第8図
企業規模と差別化行動の関係
~規模が小さい企業で、飛躍的変化を伴う新製品開発が行われている~
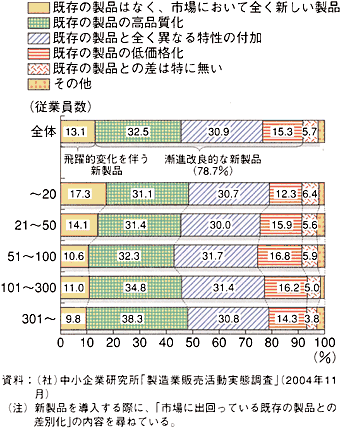
(2)新製品開発を成功する企業の特徴
製造業にとって、「新製品」開発の効用が高いことは既に過去の中小企業白書で述べてきているところである。しかしながら、企業は常に新製品開発を成功させているわけではない。むしろ、「失敗は成功の母」と言われるように失敗を教訓として成功を収めているケースもある。このように新製品開発において、失敗も加味した上で成果を上げる企業は、新製品開発への取組姿勢や技術・ノウハウ・販売などの経営資源に優位性があると考えられる。では、新製品開発に成功する企業はどのような優位性があるのであろうか。
競合他社に対する経営資源の優位性として「企画・提案能力」「価格競争力」等、企業属性として「恒常的に新しい商品の企画・開発に取り組む人材の有無」「市場での認知度」等のそれぞれについて、新製品開発の成果を上げている企業と上げていない企業の差をみると「企画・提案の能力」、「独自性のある商品を提供」、「先進性のある技術の導入」が大きい(第9図)。中小企業の新製品開発においては、中小企業の「強み」である柔軟さや機動性に加え、このような「強み」を持っている企業が成功するのである。
第9図
新製品開発に成功する企業の特徴
~新製品開発を成功させるには、企画提案力、独自性、先進性といった「強み」を育てることが重要~
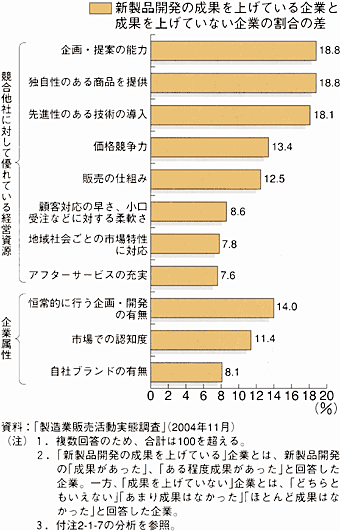
2.新たな創造を産み出す事業連携
(1)中小企業で行われる連携の状況
自社単独で「経営革新」を行うよりも、他社との連携を通じて自社の「強み」を持ち寄り、不足する経営資源を相互に補完することで、このような市場ニーズに対応する方が効率的である中小企業も現れ始めている。
こうした動きは「事業連携」という形で行われるのであるが、このような連携の形は大きく2つに分類できる。1つは大学、研究機関等との産学官連携により高度な技術革新を行う「開発型連携」であり、もう1つは「分業型連携」である。分業型連携は、従来からみられる組合による横の連携ではなく、それぞれの企業又は機関が開発・生産・販売等の得意な分野を相互補完しながら連携体制を築き、工程管理や擦り合わせを行うことにより、より市場ニーズに近いところで、高度・高付加価値製品の生産を行う形態である。現在の中小製造業における連携の実施状況を企業規模別にみると、おおむね「開発型連携」に取り組んでいる企業は2割弱、「分業的連携」に取り組んでいる企業は2割前後で、7割弱の企業は取り組んでいない(第10図)。
第10図
中小製造業の連携の状況
~連携を意識して取り組む中小製造業は3割程度~
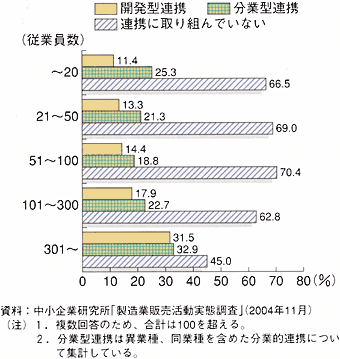
(2)事業連携の効果

事業連携を行っている企業に「連携体の具体的効果(期待する効果)」を尋ねたところ、「新商品開発力・製品企画力・技術開発力の向上」「販路の拡大、市場開拓能力の拡大」「売上・付加価値の拡大」といった高付加価値化を目的としたものが多い(第11図)。
事業連携は高度でかつ市場ニーズに対応するための取組であるが、具体的にはどのような企業や機関との連携が効果があるのであろうか。事業連携による経営革新を行った企業と、単独で経営革新を行った企業の経常利益の増減傾向を比較すると、より高度な技術化を図る「大学、研究機関等との連携」、市場ニーズと直接結びつく「販売先との連携」は、単独で行う経営革新より増加傾向の割合が高い(第12図)。
「開発型連携」の代表的な形態である産学官連携で、高いパフォーマンスがみられる背景には、中小企業において不足する基礎研究を大学、研究機関等が補うことで、より高度で新規性のある新製品を産み出していることが挙げられる。実際、第13図によると、大学・研究機関等との事業連携は、他の事業連携に比べて新規性のある製品を産み出している割合が高い。このように中小企業の新製品開発において大学・研究機関等との協力関係は有用な連携活動であり、今後も積極的な活用が望まれる。
第11図
事業連携に期待する効果
~事業連携により高付加価値化を期待している企業は多い~
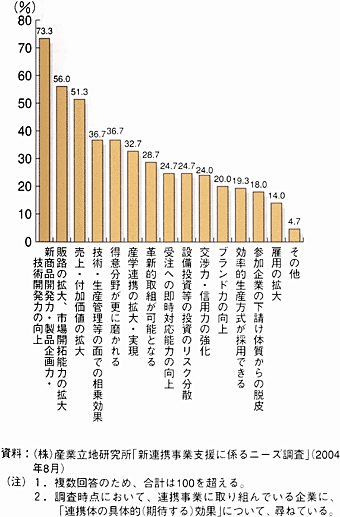
第12図
事業連携による経営革新の効果(経常利益)
~高度な技術化を図る産学連携、市場ニーズに結びつく販売先との連携は、
経営革新の効果を高める~
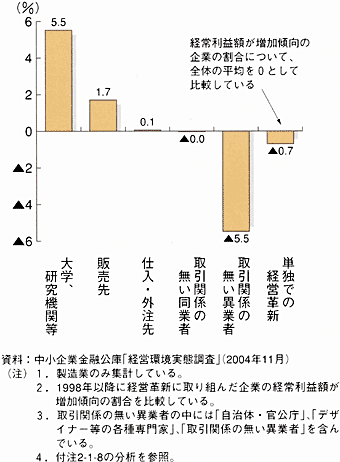
第13図
連携による研究開発と新製品の新規性
~世の中に新しいものを産み出す上で、産学連携の効果は高い~
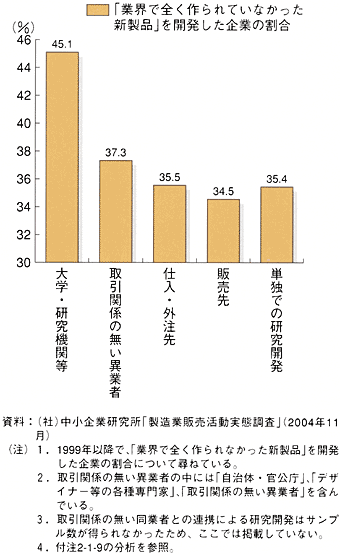
(3)新しい事業連携の形
我が国の中小製造業では、高度・高品質な部材を提供するために、ものづくりに不可欠な要素技術の現場レベルでの擦り合わせが行われているが、こうした事業連携はコスト削減を目的とした単なる経営資源の相互補完に留まらず、川上行程から川下行程までの異分野の技術やノウハウの融合によって、単独の企業や研究者の従来型の発想を超えた「新しい事業連携」に変化しつつある。具体的には(事例4)でみられるように、それぞれの「強み」がある他のメーカーと事業連携を組むことにより、新たな製品が産み出されていることが分かる。
このように、特定分野においては他社が容易に真似出来ない卓越した技術を持ち、小規模がゆえに可能となる柔軟かつ機動的な事業展開を行うことは、変化の早い経済環境の中では最大の武器となる。このため、中小企業が経済社会の激しい地殻変動・構造変化をビジネスにおける障害や制約ではなく、成長の機会へと転換するために、優れた技術・ノウハウを有する他の企業等との連携活動は重要である。特に製造業で行われている「摺り合わせ」はマーケットを囲い込む有効な手段である。「摺り合わせ」の結果産まれる商品を模倣することは容易でなく、このような連携の深化が大きなイノベーションを産み出している。
こうした新たに出現しつつある事業連携の特徴は以下の①~④であり、前出の「中小企業新事業活動促進法」ではこれらを特に強力に支援していくこととしている。
①異なる知見の融合
中小企業が日々変動する多様化した市場の要請に的確に応えるためには、自らの事業分野における従来の経験のみに頼るのではなく、分野の異なる知見・技術・ノウハウ等を有する他社と連携し、これらの経営資源を有効に組み合わせることにより、一体的に事業を行っていくこと
②多様な主体との連携
前項で述べたような基礎研究や、販路開拓のノウハウに不足する中小企業の連携相手としては、他の分野の中小企業のみならず、中堅・大企業や国・地方の研究機関、大学等の多様な主体と連携すること
③中核企業の存在
連携が有効に機能するためには、発注元や販売先との交渉において責任主体が明確になること、窓口の一元化により調整コストが削減されることが重要である。また、製品の研究開発、製造工程から販売、サービスの企画から提供まで、事業活動全体を統括・管理し、事業者間の緊密な連絡・調整を行う主体が不可欠である。従来の下請的な関係と異なり、こうした主体が中核的なリーダー企業となり、緩やかな連携体を築くこと
④一定のルールの存在
緩やかな連携であっても、それぞれの参加企業が、意思決定、責任分担、技術水準・品質保持能力等に関する一定のルールを持ち、有効なガバナンスの仕組みを確立すること

D社(栃木県、従業員76名)は、コネクタ等の自動車部品を扱う鍛造業者。自動車部品鍛造は従来、アルミニウムで作られていたが、激しい価格競争、技術の陳腐化により、従来の機能を超える軽量、高機能の部品開発や製品開発の高速化が求められている。このようなニーズに応えるため、新たな合金技術を軸とした鍛造品の開発のための材料メーカー、量産化のための機械製造技術を有する機械設計メーカーと連携を組むこととなった。また、技術シーズの提供や特許開発内容の妥当性評価、開発実行段階での調整を行う研究機関として、産業技術総合研究所とE大学の教授にアドバイザー的役割として参加して貰った。
【研究機関、大学の主な役割】
自動車部品鍛造に関する技術内容は年々高度化しており、当社内で基礎技術開発から全て行うには、資金的にも人材的にも難しくなってきた。そこで、研究機関や大学で研究されている技術シーズを利用することで、不足する技術を補い、こうした高度技術に対応しようと考えたのであるが、実際に研究所や大学教授にアドバイスを貰うようになってからは、技術シーズの提供だけでなく、開発の初期段階でその方向性が妥当であるかの技術評価・アドバイスなど技術開発に関する総合的な支援を受けており、製品開発をより効果的に行うことが可能となった。
【事業連携による相乗効果】
一方、事業連携を行うことで得たメリットは、各部品メーカーが持つ情報を共有化することで、自動車メーカーのニーズ情報がより具現化したことである。
従来は、材料メーカーは材料に関する情報、加工メーカーは加工に関する情報しか入手できなかったが、事業連携を組むことで、自動車全体で求められていることが分かるようになった。そして、全体の情報が入手できるようになると、①情報の確実性が増し、開発段階での当たり外れがなくなったことから製品開発の効率性が増した②分野の異なる複数の技術が組み合わさることで、機能財と高強度・高精度品の両面を備えた製品を素早く供給することが可能となった等の効果があった。現在、内容によっては、自動車メーカーの要求する水準を超えて、逆に部品メーカー側から製品を提案することも多くなり、事業連携による相乗効果は非常に大きいものとなっている。 |

F社(高知県、15名)は、四万十川上流地域で作られた大豆のみを使った独自の豆乳クリームを開発するメーカー。アメリカを中心とした輸入大豆のほとんどは遺伝子組み換えのものである中、同地域産の大豆を100%使用しているA社の豆乳クリームは品質的に安全でかつ質が高い。従来、豆乳は凝固する特質があったが、F社の豆乳クリームはとける、まざるという特徴を残しながら豆乳の甘みを出し、凝固作用を取り除くことに成功し、様々な商品への利用が可能となっている。
【事業連携のきっかけ】
F社は元々普通の惣菜一次加工メーカーであったが、大手メーカーとの競争が激しくなり、価格勝負では太刀打ちできない状況であった。社長は豆腐屋で働いていた経験を生かして「豆乳クリーム」を開発した。しかしながら、豆乳クリーム自体は一般に普及していないがゆえに、なかなか顧客に受け入れられるものではなかった。こうした中、単純に豆乳クリームそのものを売るよりも、食材として販売した方が受け入れられやすいということが分かり、食材と販売することとした。
ところが、F社自体はパンメーカーでも菓子メーカーでもないので、こうした食材を作る技術・ノウハウもなければ、そのための設備投資を行う余裕も無い。それよりもむしろ、食材のことは食材のプロに任せた方が、より良い商品が提供できると考え、食材メーカーとの連携を始めたのである。こうした事業連携により生まれた商品の販売は、「ディスカウントしない方針」等の商品価値の維持や販売戦略を重要視していることから、当社が一元的に行っている。
【新しい連携によって広がる無限の可能性】
連携相手企業は、豆乳クリームの原材料供給メーカー、麺類メーカー、洋菓子メーカー、蒟蒻メーカーと多種多様であることから商品開発の幅が格段に広がり、豆乳クリームを利用したパン粉、ドーナツ、大豆丸ごとコロッケ、麺類、蒟蒻等を開発し、地元スーパーに納めている。また、かつてF社は大手食品メーカーとの取引において1社単独では対応できなかった経験があるが、現在はスピーディでかつ高付加価値な商品を提供することが可能となった。今後は、豆乳クリームを利用したハンバーガー、マーガリンといった食品への応用だけでなく、化粧品関連にまで応用する計画であり、新たな事業連携先を求めている最中である。こうした事業連携によって、当社が扱う商品の可能性は無限に広がっていくのである。 |
マーケットを見据えた販路開拓
(1)中小企業でも重要となるブランド戦略

価格競争が激化している近年では、販売促進活動を効果的に行うために、「自社ブランド」の取組の重要性が増している。
自社ブランドとは、自社が扱う商品名、店舗名の標章(商品ブランド)や自社名そのものの標章(企業ブランド)といい、ブランド化はこうした標章を冠することにより、他社との識別を行うことや、顧客に対して一定の品質を保証するという意思表示を行うことである。実際、独立行政法人経済産業研究所「中小企業の新しい経営活動に係る調査研究」により、自社ブランドを持っている中小企業が自社ブランドに持たせている役割をみると、「品質を保証し、安心を与える」といった保証機能が約7割と最も高く、次いで「他社の商品と分かりやすく選別させる」といった識別機能が約6割である(第14図)。
一般消費者は「ブランド」という言葉から高級宝飾品や大企業の広告宣伝に使われる標章を連想する場合が多いが、自社ブランドを上述のように定義すると、小規模企業においても39.2%が自社ブランドを持っており、自社ブランドは中小企業においても販売促進活動の一つとして活用されている(第15図)。
第14図
中小企業の自社ブランドの役割
~企業ブランド、商品ブランドの役割には、「保証機能」、「差別化機能」等が挙げられる~
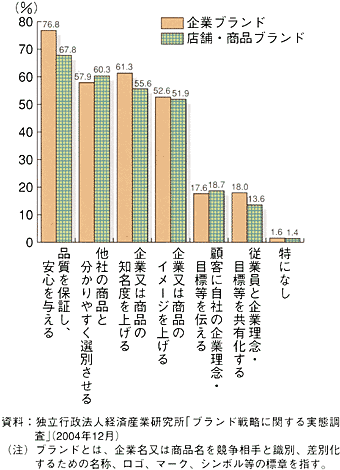
第15図
自社ブランドを持っている企業の割合
~小規模企業でも約4割が自社ブランドを持っている~
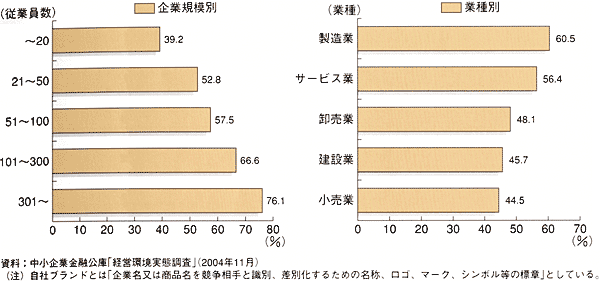
|