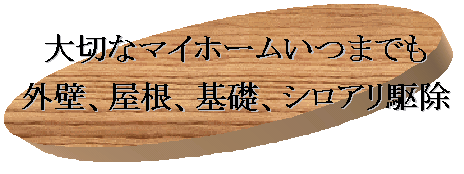

|
スレートやトタン屋根から伝統美と機能性の瓦屋根へ…
寒冷地長野県。厳しい自然条件の中で常に安心して住まわれるための耐寒耐雪瓦にしませんか。
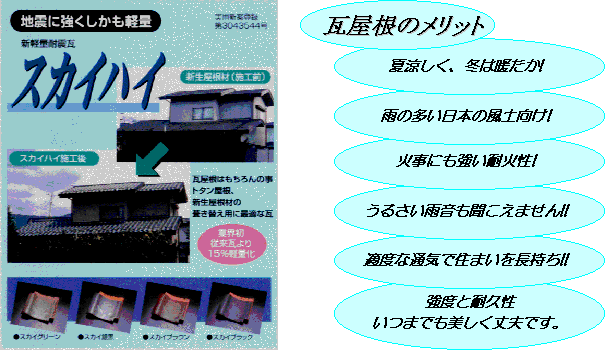
和形瓦施工納まり図をダウンロード出来ます。
こちらからどうぞ!

![]() Q1.最近いろいろな業者がセールスにきます。
Q1.最近いろいろな業者がセールスにきます。
また選択の条件としては何か
ありますか?
| A. | 色々な選択肢がありますが、社会的には”社団法人”・全日本瓦工事業連盟(略称=全瓦連)”加盟工事店であることがあげられます。 技術的には、国家資格である”1~2級瓦葺技能士” ”瓦屋根工事技師”の資格保有者のいる工事店も考慮にはいります。 尚、工事店が全瓦連盟店であって、そこにいる職人が前記の2国家資格所有者であれば、ほとんどの人は”(社)全瓦連瓦屋根診断技師”(A2参照)の資格を所有しています。 |
![]() Q2.セールスに来る人のなかに「○○屋根診断士」というような
Q2.セールスに来る人のなかに「○○屋根診断士」というような
「資格」を掲示して
いる人がいますが 、ど.ういう「資格」ですか?
| A. | 多くの資格は某大手の建材メーカーが独立のシステムで創設した民間資格です。実務経験がなくても、誰でも数日間の講習で取得できます。 それに対して民間資格扱いとなりますが、全瓦連が平成8年度に建設省の指導の元に”(社)全瓦連瓦屋根診断技士”を創設しました。この資格は公的資格である”(労働大臣認定)1~2級瓦葺技能士””(建設大臣認定)瓦屋根工事技士”の2資格がないと取得できません。 事実上国家資格並と言えます。また、事実上6年以上の実務経験者であると言えます。 ”(社)全瓦連瓦屋根診断技師”であることをしっかり認識してから話は進めましょう。 |
![]() Q3.いろいろな形の瓦がありますが、迷います。
Q3.いろいろな形の瓦がありますが、迷います。
| A. | ①.「和形」は基本的に本当に良くできた「形」です。これ以上の「形」はまず今後出ないでしょう。 更に瓦の性能を高める為に色々と改良工夫された瓦もあります。 ②.「S形」は本来急勾配用の瓦です。それだけに、五寸未満勾配屋根の、流れの長い屋根の施工においては細心の注意を必要とします。 尚、この形も色々と改良して性能を上げた瓦もあり、露水の防止に効果をあげています。 ③.「平板形」は瓦だけで雨水は取れません。露水に対して下地の施工が大事になります。 残念なことに各窯元メーカーが独自のデザイン寸法で製作しているため、各窯元メーカー間での互換性がありません。 瓦のデザインの違い等を気にしなければ、少数の窯元メーカー間で可能です。 ④.「本葺形」は全重量が「和形」に比べ2倍以上あります。 施工さえしっかりしていれば「和形」に比べ3倍は保つと言われています。 重量ならびに施工性の問題を解決するために、平丸一体形の瓦も種々出てきています。 この形も各窯元メーカー間での互換性はありません。 「純和風」をお望みならば①。「洋風」をお望みならば②、③。「格式、伝統」を重んじるならば④。といったところですが、①でも十分に「洋風」に施工できます。また③ですっきり「数寄屋風」にする方法もあります。 |
![]() Q4.地震・強風に対して心配です。
Q4.地震・強風に対して心配です。
| A. | 最低限、”住宅金融公庫融資住宅木造住宅工事共通仕様書”に従って施工すれば、かなり強い地震・強風にある程度対処できます。地震に対して、15~20%ほど軽量化された「軽量瓦」が開発されています。 強風に対しては施工方法を絡めて、尻の部分を改良しての「縦桟瓦」。噛み合わせ部分を工夫した「防災瓦」などがあります。この2種類の瓦は地震に対しても、威力を発揮します。 施工面におきましては「建設大臣評価」を受けた工法が、粘土瓦関係で5工法、厚形スレート関係で5工法あります。これらの工法は耐風面だけでなく、耐震面に対しても十分に対処できます。 いずれの工法を用いるにせよ、しっかしりた施工が必要不可欠であることはかわりありません。 |
![]() Q5.住宅用化粧スレートに含まれる、
Q5.住宅用化粧スレートに含まれる、
アスベスト(石綿)は現在も含まれていますか?
| A. | アスベストは肺ガンの元と言われて久しいですが、”脱アスベスト”は進んでいます。 アスベストのかわりに「特殊ビニロン繊維」などが使われていますが、若干強度が落ちるようです。 ここで「表示」にご注意願います。アスベストの含有量が 5%未満を”ノンアス(ベスト)”0%のものを”ゼロアス(ベスト)”と表示されています。全く紛らわしいことですね! |
![]() Q6.積雪地帯でも瓦の施工は可能ですか?
Q6.積雪地帯でも瓦の施工は可能ですか?
可能ならどんな瓦がよろしいですか?
| A. | 瓦の製造技術、性能の向上また施工技術の進歩により、極寒の地北海道でも瓦屋根が見られるようになりました。かつての二毛作地帯では問題なく施工できますが、ただ気象条件が本当に厳しい所は、瓦も施工仕様も限られてきます。 更に、最近の家は「高気密高断熱化」しているため「すがもれ」「結露」が起きやすくなっていますので、それらに対する施工が必要となります。 瓦は厳格な管理の元で製造された粘土瓦で和形につきます。セメント系では高圧プレスセント瓦でやはり肉厚の和形となります。同じセメント系でも大半の肉薄の瓦はいけません。雪の重みで瓦が割れます。 化粧(石綿)スレート系は問題外です。 施工ですが、美観より実用最優先となります。種々の補強金具、副資材等が開発されていますのでそれらをうまく使うことによりしっかりした瓦屋根が可能となります。 |
![]() Q7.現在、緩勾配(3寸)の板金葺の屋根です。
Q7.現在、緩勾配(3寸)の板金葺の屋根です。
雨音がうるさくまた色の塗り替えが
面倒です。
緩勾配でも瓦の施工は可能ですか?
| A. | 可能です。 日本屋陶器瓦協業組合 (〒395-1101 長野県下伊那郡喬木村1388-2 TEL.0265-33-2150)が開発した「スカイハイ」があります。 またこの瓦は軽量化されていますので、板金をはがさずに直接その上に葺くカバールーフ工法で行えば相当のコストダウンになります。 さらに「合体構造」でありますので、地震・強風に対しても安心できます。 |
![]() Q8.現在、化粧石綿スレート葺きの屋根です。
Q8.現在、化粧石綿スレート葺きの屋根です。
退色・風化が目立つようになってきました。
イメージチェンジをしたいと思いますが、
なにかいい方法はありませんか?
| A. | 石綿スレート瓦に含まれている石綿(アスベスト)の飛散を防止するために、瓦をはがさずに直接その上に葺く”カバールーフ工法”で施工することが一番ですが、そのための瓦としてA7で紹介した”スカイハイ”がお勧めです。 その他”㈱シバオ(〒694-0303 島根県太田市水上町白坏 658-1TEL:08548-9-0201)”が開発した”セラガード”もお勧めです。平板(ひらいた)の高温焼成の陶器瓦ですので、退色、風化、凍害は絶対に起きません。 施工に当たり、屋根裏の換気を考慮した工事を行うことができますので、大事な家の寿命を延ばすことが可能となります。 |
屋外木部は、日焼け、カビ、ホコリ、アカなどの汚れで
いつのまにか黒ずんできます。この汚れを洗浄し、
白木の美しさと、てざわりを取りもどし、
なおかつその美しさを長く保つために、
日焼け防止、防虫、防腐処理を施します。
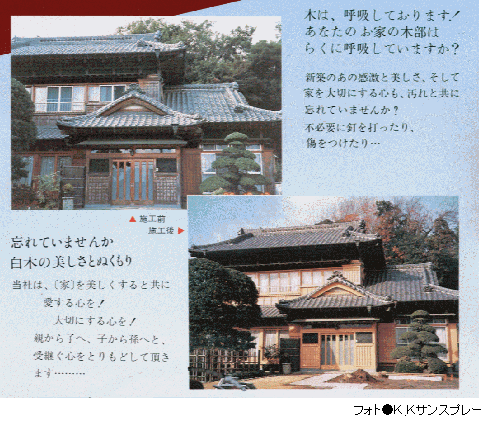

屋根・外壁の塗装から浴室の防カビ塗装・断熱工法・内装・クリーニングなど修繕工事はなんでもご相談ください。

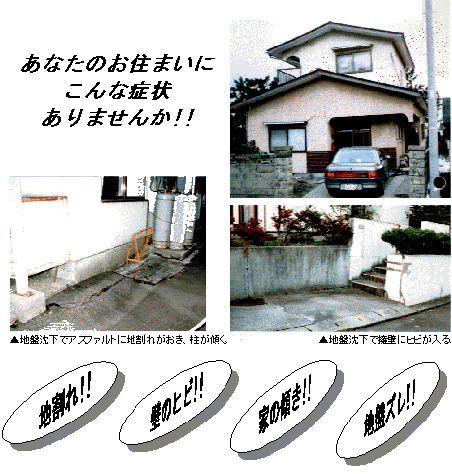
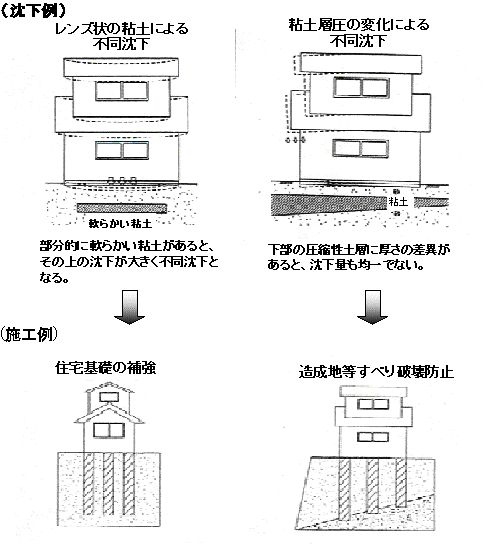
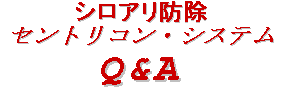
![]() Q1.薬剤の有効成分ヘキサフルムロンは、
Q1.薬剤の有効成分ヘキサフルムロンは、
いつごろ効果を発揮するのですか?
| A. | シロアリの職蟻は年に5~6回程度必ず脱皮するのですが、ヘキサフルムロンを摂取したシロアリは、脱皮ができなくなり死に至ります。脱皮した時期にはじめて効果を発揮するので、職蟻取したあとでも、 フェロモンにより仲間を誘導することができるのです。 |
![]() Q2.コロニー(巣)の全部のシロアリが薬剤を摂取するのですか?
Q2.コロニー(巣)の全部のシロアリが薬剤を摂取するのですか?
| A. | 薬剤を摂取するのは、採餌活動をする職蟻です。フェロモンにより誘導されて職蟻のほとんどが有効成分ヘキサフルムロンを摂取し、死に至りますが、それによって餌を与えられる兵蟻、幼虫なども死ぬことになり、 コロニー(巣)全体が崩壊します。 |
![]() Q3.セントリコン・システムは、
Q3.セントリコン・システムは、
機材さえあれば自分でも使用できるのでしょうか?
| A. | セントリコン・システムの施工には、シロアリの生態に関する知識と技術が必要なので、専門業者におまかせください。特に、シロアリをベイトカップに移す作業などの際、シロアリに刺激を与えると、仲間をベイトカップから遠ざける信号「警報フェロモン」を発し、システムが効果を発揮できなくなります。 |
![]() Q4.従来の薬剤散布のほうが、一斉にシロアリを死滅させられるのでは?
Q4.従来の薬剤散布のほうが、一斉にシロアリを死滅させられるのでは?
| A. | シロアリのコロニー(巣)は地中にあり、また家屋から離れたところにある場合もあるので、従来工法では完全にコロニーを崩壊させることは困難です。むしろ、薬剤のバリアをつくることで、家屋への侵入を防ぐだけのものとお考えください。 |
![]() Q5.シロアリが家屋に生息しているかどうか、わからないのですが…。
Q5.シロアリが家屋に生息しているかどうか、わからないのですが…。
| A. | シロアリがいる家屋には、繁殖期に羽アリが発生します。 4~6月の雨上がりの昼間に出る場合はヤマトシロアリ。 6~7月の夜の場合はイエシロアリです。羽アリが飛んでいるのを見たら、 防除の対策をとる必要があります。 |