|
特集「知的財産と中小企業」その2
商品の流通秩序を護るために
「知的財産権」とは、人間の頭脳や感性などから生み出された技術やアイデア、デザイン、芸術作品など、形のない成果に関する権利であり、技術革新とイノベーションの源泉だ。わが国では、知的財産の創造や活用の促進を図ろうと2002年「知的財産基本法」が制定され、特許重視の政策を推進。保護の重要性が広く認識されるようになった。
長野県は特許出願件数でつねに全国上位に位置する。意欲的で技術力の高いものづくり企業が多いことを裏づけているが、しかしその一方で、関心は高くても、特許取得にかかる費用や時間を考え二の足を踏むケースが多いことも事実。さらに保有する独自技術やアイデア等を知的財産として有効活用している企業となると、まだまだ少ないのが現状だろう。
そこで本特集では、長年にわたり県内を中心に活躍し数多くの事例を扱う日本弁理士会東海支部長野委員会委員長綿貫隆夫弁理士(綿貫国際特許・商標事務所長)に執筆をお願いし、前号から3回にわたって知的財産権と中小企業との関わりについて取り上げる。
前号の第1回と第2回では特許権、意匠権、商標権、著作権、実用新案権といった知的財産各権利とともに、中小企業が日頃疑問に感じているポイントを実例を交えながら分かりやすく解説する。第3回は知的財産活用の成功事例を紹介。さらに知的財産権をめぐる新たな動向として、経済産業省が策定した「特許審査改革加速プラン2007」についてもふれる。
知的財産をいかにビジネスに活かし、企業発展の原動力とするか。そのヒントになれば幸いである。
商品の流通ルートを確かに確保する
他の業者に比べて優れた商品を提供する業者は、自分のところの商品を他の業者の商品と区別するために、自分の商品に独特の「印」を付ける。優れた品質を維持・向上させる業者に対し原価の安い粗悪な商品を作り、人気のある優れた商品と同じような「印」を付けて販売すれば、真面目な努力もせずに、企業努力をして人気を保っている企業の利益を掠め取り、てっきり同一の商品だと思って購入した顧客の期待を裏切ることにもなる。顧客の満足のために努力する業者が報いられ、顧客も購入の安全が保障されるためには、商品に付けた「印」を何らかの手段で保護する必要がある。この「印」を商標と呼び、ある種の商品についてはその業者だけが特定の商標を付すこととし、他人にはその種の商品に紛らわしい商標の使用を禁ずることにより流通の秩序を護っていこうとする制度が法で定められている。
これは一つは不正競争防止法であり、他の一つは商標登録制度であり、商標を登録することで独占使用を徹底させる。
商標Gメン
昔デパートで衣類の安売り場に人が群がり、われ先に取り合いをする光景があった。商品にれっきとした有名ブランドが付いている。だが低品質の商品に同じ商標をつけた偽物がトラックに積まれてきて、安売り場に混ぜ込まれ、トラックはどこかへ消え去って行った。買った衣類は一度洗濯すると、ちりちりになって着られない。正当な商品を作っているメーカーは商標Gメンを雇ってニセモノを作っている作業所を突き止め、警察の手を借り、商品を押さえ刑事事件に持ち込んだ。今でも海外からこの手の商品が日本に入り込んで来るので、日本当局は水際での取り締まりにやっきとなっている。
商標登録制度
商標登録するには、使用したい商品とマークを指定して特許庁へ出願する。特許庁の審査で過去に同一・類似の商品に対し出願商標と同一・類似の商標が登録されていないかどうかを調査する。同一・類似関係にある登録商標が見出されなければ登録され、独占使用の地位を得る。
勝手なネーミングは危険!
よく思い付いただけで自分の商品にネーミングして、登録商標があるかどうかも調べないでその商標を付けて売り出す人がある。既に登録商標があれば絶対に救われない。使用状態が長年続いても、言い訳にはならない。やめろといわれれば即、使用を停止し、これまでの無断使用に対する損害を賠償しなければならない。商標登録制度は独占権を認めると同時に登録商標の存在を公示するので調査義務がある。登録商標の存在を知らなかったからとかマーケットに見当たらなかったからといっても許されない。どうしてもやめられない状況にあれば高額で買い取るか、借りるなどすることになる。
商品に新しいネーミングをするときは何としても登録商標の存否調査をしなければならない。法治国家である。権利侵害を起こせば、商標を変更するために企業が蒙る様々な損失。これまで顧客の記憶にあった商品が市場から無くなるうえに損害賠償、罰金、懲役などの刑事罰を受ける。
サービスマークも商標
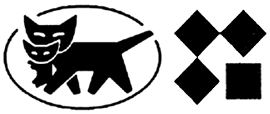 商標を使用する対象にはホテル、レストラン、輸送、金融、医療、教育など人や施設の提供のようなサービス(役務)も含まれる。ヤマト運輸のクロネコのマークや八十二銀行の4つのダイヤ形のマークなどサービスマークとして登録商標となっている。 商標を使用する対象にはホテル、レストラン、輸送、金融、医療、教育など人や施設の提供のようなサービス(役務)も含まれる。ヤマト運輸のクロネコのマークや八十二銀行の4つのダイヤ形のマークなどサービスマークとして登録商標となっている。
最先の商標出願をした人が同一類似の範囲まで押さえる
商標登録の出願は最初に出願した人が登録される。以後に同一・類似の関係にある商標は登録されない。他人が出願して登録を受ければそれまで使用していた者も、先使用権などが認められない限り使用できなくなる。登録商標や出願中の商標の調査は取り敢えず特許庁の電子図書館により検索できる。
出願前の商標が、発明のように発明者の同意を得ない人が出願したり、出願前に公知だったものが出願されたという理由で登録されないことは無い。したがって、商標登録しようと思っている商標を出願前に他人に知らせてしまい、先に出願されても救いようが無い。
ネーミング決定の段階で企業の情報を手に入れた人が、企業の先を越して、大急ぎで出願し、その後から出願した企業は先願があるとは知らず、広告宣伝や包装箱を作るなどの準備を進めたが、後になって先登録をした人がいることがわかって大騒ぎになり、結局高い費用を払って買い取らされた事例を題材にした小説がある。
はじめから商標登録の対象にならないものもある
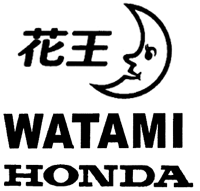 商品(洗剤)について「アタック」や役務(レストラン)について「和民」などはそれぞれ他人の商品や役務と識別できる商標であるから登録の対象になる商標ということができるが、商品(りんご)に「赤いりんご」とか役務(ホテル)に「お休み処」などは商標として個性あるネーミングではない。「東京羊羹」なども東京は地名、羊羹は普通名称であるから誰かの独占使用を認めるべき言葉ではない。このような商標は登録されない。また、日の丸や外国の国旗、赤十字など特定人に登録を認めるべきではないものも排除される。もっとも、これまでも(自動車)の「HONDA」などありふれた氏ではあるが、独占的な使用により全国的に周知で、他に商標「HONDA]が(自動車)に使用されている事実が無いことから例外的に商品の識別力を認めているものがある。 商品(洗剤)について「アタック」や役務(レストラン)について「和民」などはそれぞれ他人の商品や役務と識別できる商標であるから登録の対象になる商標ということができるが、商品(りんご)に「赤いりんご」とか役務(ホテル)に「お休み処」などは商標として個性あるネーミングではない。「東京羊羹」なども東京は地名、羊羹は普通名称であるから誰かの独占使用を認めるべき言葉ではない。このような商標は登録されない。また、日の丸や外国の国旗、赤十字など特定人に登録を認めるべきではないものも排除される。もっとも、これまでも(自動車)の「HONDA」などありふれた氏ではあるが、独占的な使用により全国的に周知で、他に商標「HONDA]が(自動車)に使用されている事実が無いことから例外的に商品の識別力を認めているものがある。
地域団体商標の登録
平成18年4月から、地域団体商標登録の制度がスタートした。これはご当地独特の産品やサービスなどでこれまでは地域名+普通名称のように登録を認められなかった商標でも、その地域の事業者の事業組合(農協など)が一体となって商品、役務の魅力を高め、有名度が高まってきたところでその組合に団体商標登録を認めるものである。たとえば「富士宮やきそば」などがその例である。長野県では「市田柿」、「諏訪味噌」、「信州鎌」、「木曾漆器」、「飯山仏壇」、「戸隠そば」、「佐久鯉」など沢山の地域団体商標が出願されて、地域の経済活動の活性化が期待されている。
商標は企業とともに育つ
商標は登録により独占使用できるので、企業努力により著名になりいわゆるブランド化する。しかし北海道の銘菓「白い恋人」のように、いったん市場の信用を落とすと著名なだけに企業ダメージも大きい。商標は企業の「暖簾」である。登録商標は独占使用が法で護られているだけに企業活動を通して「暖簾」に傷をつけることなくブランドにすれば大きな無体財産である。
商標登録制度以前の不正競争防止法
特許庁の商標登録はこれから使用して商標を育てようとする者でもまずは登録を認めるものであるが、登録されていない商標でも、特定の者の商品やサービスを表す標識(印)として取引の場で顧客や関係者に十分に知れわたっているものであれば、保護されるべきである。自分の商標を紛らわしく使用されて、商品、サービス、営業の混同を起こされたものは不正競争防止法によって差し止め請求や損害賠償の請求を認められることがある。
商標に限らず、商品の包装形態や色彩など商品、サービス、営業などを区別するための目印についても問題にされることがある。
新しい商品デザインは意匠登録で優位に
同じ用途の商品AとBでも、商品Aの方がデザイン的に魅力があれば顧客の手はAに伸びる。並べて置いても、商品Aの売上はBと大きな差が付く。商品Bを製造するメーカーはデザインをAに近づけたくなる。物品Aについて意匠登録が取られていれば最長20年間同一類似の外観の競合品を近づけない。意匠登録はデザインの斬新さだけではなく、人気が継続すればブランド的な価値も重要視される。意匠登録の対象には完成品のほか独立して取引の対象になれば部品でもよい。これまでも中小企業者の中には最終メーカーに納める部品の意匠登録をして競走上優位に着くこともある。また、完成品や部品のみならず、物品のある部分に意匠的に大きな特徴があれば、その部分が物理的に切り離せない部分であっても他の全体を点線で現して登録される場合がある。
中心となるデザインを本意匠とし類似する意匠を関連意匠として登録を受けることもでき、これにより権利範囲が広がり且明確になるため模倣を阻止しやすくなる。
著作権が存在する商品は無断で複製できない
量産品の基となるデザインが美術品のレベルであれば著作権が認められ、これをコピーすることにより量産することは、著作者の承諾を得ない限り認められない。著作物を商標や意匠に利用している場合は、商標登録、意匠登録を得たとしても、その著作者の承諾を得なければ使用または実施をすることが出来ない。
実用新案登録制度の利用
 中小企業としては実用新案登録は時に特許制度より手っ取り早いことがある。技術的な考案が物品の形状、構造または組み合わせとして具備されている場合、たとえば「吸盤の付いた歯ブラシ」などである。出願すると無審査で登録される。権利が生ずれば出願日から10年間、他人の実施に対して一応の牽制力がある。ただし、権利を行使する場合には特許庁の審査官の作成する実用新案技術評価書の提示が必要である。 中小企業としては実用新案登録は時に特許制度より手っ取り早いことがある。技術的な考案が物品の形状、構造または組み合わせとして具備されている場合、たとえば「吸盤の付いた歯ブラシ」などである。出願すると無審査で登録される。権利が生ずれば出願日から10年間、他人の実施に対して一応の牽制力がある。ただし、権利を行使する場合には特許庁の審査官の作成する実用新案技術評価書の提示が必要である。
|