|
監事の権限拡大、監事の権限限定と組合員の権限拡大
- 監事の権限拡大
監事の権限が拡大されます
これまで監事は、会計に関する監査のみを行うこととされていましたが、今後、監事は原則として、会計監査に加え、業務監査(理事の業務執行の監査)も行うことになりました。このため、理事や使用人等に対する組合事業の報告請求や業務、財産や総会提出議案の調査権限が与えられるほか、組合と理事間の訴訟の際に組合を代表する権限が与えられます。
理事会への出席など義務が強化されます
監事の権限強化に伴い、理事長に対しては、監事に理事会の招集通知を発する義務が課されるとともに、監事に対しては理事会への出席と理事会の議事録への署名、記名押印義務が課されるなど、権限が強化されます。
この場合、理事会議事録への記載事項も追加されますので、留意することが必要です。
経過措置に留意する必要があります
この変更は、事業年度が4月に開始される組合の場合、平成20年4月以降に開催される平成19年度決算に関する通常総会終了の後に適用されます。現行中協法においては監事の権限は会計監査に限定されています。したがって、この経過措置期間中に監事の権限を業務監査にまで拡大(行政庁に対し停止条件を付した定款変更の認可申請を行うことも含む)することはできないことに留意する必要があります。
なお、監事の権限を従来の会計監査のみから業務監査にまで拡大する場合は、その時点で一旦監事の任期が終了することに留意する必要があります。
- 監事の権限の会計監査への限定と組合員の権限拡大
組合員数1,000人以下の組合は監事の監査権限を会計に関する監査に限定することができます
すべての組合の監事に原則として業務監査権限が付与されますが、組合員数(連合会の場合は会員組合の組合員の合計)が1,000名以下の組合では、定款にその旨を定めることで、これまでどおり監事の権限を会計に関する監査に限定することができます。
この場合の組合員数が1,000人以下であるかどうかの判断は、法施行後開始する事業年度の開始の時点で判断することとなります。
また例えば、平成19年度の開始時点で1,000名以下であった組合において翌20年度の開始時点で1,000人を超えた場合には、その年の5月の通常総会の終了時までは1,000人を超えない組合であるとみなされることから、通常総会で定款変更を行うとともに停止条件を付して監事の改選を行うこととなります。
逆に1,000人を超えている組合が翌事業年度の開始時に1,000人以下となった場合であって、今後、業務監査権限を与えないこととしようとする場合も、その年の通常総会において定款変更を行うことで対応することが可能です。この場合は監事が任期途中であっても改選を行う必要はありません。
現在の定款規定のままで監事の権限が会計に関する監査に限定されているとみなされます
この監事の権限を会計に関する監査に限定する旨の定款の規定については、組合の現在の定款の中の「監事の職務」に関する規定が全国中小企業団体中央会策定の定款参考例と同様の規定となっている場合には、「監事の権限が会計に関する監査に限定される」規定であると考えられることから、特段、定款変更する必要はありません。
逆に、監事に会計に関する監査に加え、業務監査の権限を付与する場合には、その旨を追加するか「監事の職務を会計に限定している」とみなされる現在の定款の規定を、削除する必要があります。
〈定款参考例〉
●監事の職務を会計監査に限定する場合
(監事の職務)
第○条 監事は、いつでも、会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事及び参事、会計主任その他の職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
- 監事は、その職務を行うため特に必要があるときは、本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
●監事の職務を会計監査に限定しない場合
(監事の職務)
第○条 監事は、理事の職務の執行を監査する。
- 監事は、いつでも、理事及び参事、会計主任その他の職員に対して事業に関する報告を求め、又は本組合の業務及び財産の状況を調査することができる。
組合員の権限が強化されます
一方で、これまでどおり監事の権限を会計に関する監査に限定する場合には、組合員に理事会の招集請求権が与えられるなど、監事の業務監査権限に相応する権限が組合員に与えられます。
総会・理事会議事録の記載事項等が異なることに留意することが必要です
監事の権限が会計に関する監査に限定されるか、理事の業務の監査にまで拡大されるか(前述)によって、総会議事録の記載事項や理事会議事録の記載事項が異なってきますので、注意が必要です。
なお、監事の権限が会計に関する監査に限定されている場合には、理事長が監事に対して理事会の招集通知を発する義務や監事が理事会へ出席し、理事会の議事録へ署名、記名押印する義務は課されていませんが、実際に監事が理事会へ出席した場合には、中協法施行規則上にその旨の規定がないことから、理事会議事録への署名、記名押印義務等が課されることとなります。
〈定款参考例〉
(総会の議事録)
第○条 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成するものとする。
-
前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)招集年月日
(2)開催の日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)組合員数及び出席者数並びにその出席方法
(5)出席理事の氏名
(6)出席監事の氏名
(7)議長の氏名
(8)議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(9)議事の経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数)
(10)監事が、総会において監事の選任、解任若しくは辞任について述べた意見、総会提出資料に法令、定款違反若しくは、著しく不当な事項があるとして総会に報告した調査の結果又は総会において述べた監事の報酬等についての意見の内容の概要
(11)監事が報告した会計に関する議案又は決算関係書類に関する調査の結果の内容の概要
(注)第2項(10)は監事に業務監査権限を与える組合における規定であり、(11)は監事の職務を会計に関するものに限定する組合における規定であるので、組合によって、適宜、選択すること。
(理事会の議長及び議事録)
第○条 理事会においては、理事長がその議長となる。
- 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成し、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印するものとし、電磁的記録をもって作成した場合には、出席した理事及び監事は、これに電子署名を付するものとする。
- 前項の議事録には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
(1)招集年月日
(2)開催日時及び場所
(3)理事・監事の数及び出席理事・監事の数並びにその出席方法
(4)出席理事の氏名
(5)出席監事の氏名
(6)出席組合員の氏名
(7)議長の氏名
(8)決議事項に特別の利害関係を有する理事の氏名
(9)議事経過の要領及びその結果(議案別の議決の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏名)
(10)監事が、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときに理事会に報告した内容及び理事会に出席して述べた意見の内容の概要
(11)理事会の招集を請求し出席した組合員の意見の内容の概要
(12)組合と取引をした理事の報告の内容の概要
(13)その他(理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨)
①招集権者以外の理事による招集権者に対する理事会の招集請求による理事の請求を受けて招集されたものである場合
②①の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したものである場合
③監事の招集を受けて招集されたものである場合
④③の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したものである場合
⑤組合員の招集を受けて招集されたものである場合
⑥⑤の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした組合員が招集したものである場合
- 次の各号に掲げる場合の理事会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
(1)組合が、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなした場合には、次に掲げる事項
①理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
②①の事項の提案をした理事の氏名
③理事会の決議があったものとみなされた日
④議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(2)理事が理事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知し、当該事項を理事会へ報告することを要しないものとした場合には、次に掲げる事項
①理事会への報告を要しないものとされた事項の内容
②理事会への報告を要しないものとされた日
③議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
(注)第3項(10)、(13)③・④は、監事に理事の業務監査権限を与える組合に対する規定であり、(11)、(13)⑤・⑥は、監事の職務を会計に関するものに限定している組合に対する規定であるので、組合によって、適宜、選択すること。
会計帳簿等の保存の義務化、会計帳簿の閲覧請求要件の緩和
会計帳簿について、会計帳簿の閉鎖後10年間の保存が義務づけられました。また、会計帳簿の閲覧請求要件が、総組合員の「10分の1」から「100分の3」に緩和されました(定款でこの割合をさらに緩和することも可能)。ただし、共済事業を行う組合及び信用協同組合・連合会については、「100分の3」は「10分の1」とされています。
〈定款参考例〉
(会計帳簿等の閲覧等)
第○条 組合員は、総組合員の100分の3以上の同意を得て、本組合に対して、その業務取扱時間内はいつでも、会計帳簿又はこれに関する資料(電磁的記録に記録された事項を表示したものを含む。)の閲覧又は謄写を請求をすることができる。この場合においては、本組合は、正当な理由がないのにこれを拒むことができない。
(注)総組合員の同意の割合については、100分の3(共済事業を実施する組合においては10分の1)を下回る割合を定めることができるので、100分の3(共済事業を実施する組合においては10分の1)を下回る割合とする場合には、当該割合を記載すること。
施行規則に基づく決算関係書類、事業報告書、監査報告の作成
これまで、組合が作成しなければならない決算関係書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案)や事業報告書、監査報告については、法令上に特段の作成基準が示されていませんでした。
これらについて、主務省令(施行規則)に基づき作成することが義務づけられ(中協法第40条、前掲)、具体的な作成基準が定められました。
- 中協法施行規則
決算関係書類(第3節(第45条~82条))、事業報告書(第4節(第83条~87条))、決算関係書類及び事業報告書の監査(第5節(第88条~97条))
- 中団法施行規則
決算関係書類(第3節(第17条~45条))、事業報告書(第4節(第46条~49条))、決算関係書類及び事業報告書の監査(第5節(第50条~53条))
これらの決算関係書類、事業報告書、監査報告の様式は施行規則に示めされておりませんので、個々の組合で施行規則の該当条文を理解し作成することが必要です。
施行規則で示された区分等を踏まえた決算関係書類、事業報告書の様式例としては、次のようなものが考えられます。なお、この様式に示した個々の勘定科目や項目の中の網掛けの部分以外については、省令施行後最初に到来する決算期において、それぞれの書類に記載が義務づけられておりません。また、勘定科目については従来から全国中央会が示してきた中小企業等会計基準と今回の改正省令を参考に作成しており、省令に規定する勘定科目をすべて網羅したものとはなっていません。したがって、今後改訂を予定している中小企業等協同組合会計基準において修正される可能性があることにご留意ください。
また、省令の施行前に到来した決算期に関して組合が作成する貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案、事業報告書については、この規則に沿って書類作成を行う必要はありません。
監査報告については、特段の経過措置が設けられていないことから、施行規則に基づき作成する必要があります。
|
<財産目録様式例>(全組合対応)
財産目録
平成 年 月 日
一 資産の部
| I 流動資産 |
| |
流動資産計 |
×××× |
II 固定資産
i 有形固定資産 |
| |
有形固定資産計 |
×××× |
| ii 無形固定資産 |
| |
無形固定資産計 |
×××× |
| iii 外部出資その他の資産 |
| |
外部出資その他の資産計 |
×××× |
| |
固定資産計 |
×××× |
| III 繰延資産 |
| |
繰延資産計 |
×××× |
| |
資産合計 |
××××× |
二 負債の部
| I 流動負債 |
| |
流動負債計 |
×××× |
| II 固定負債 |
| |
固定負債計 |
×××× |
| |
負債合計 |
××××× |
三 正味資産の部
| I 正味資産 |
×××× |
| |
(注)時価評価による組合正味資産の価額は××××である。
なお、時価評価額の計算は、土地については固定資産税評価額倍率方式を採用し、建物等については簿価から過去の減価償却不足額を控除した額にした。
平成○○年度土地固定資産税評価額 ××××
土地時価相当額 ××××
(固定資産税評価額を時価の○○%程度とみて、固定資産税評価額を○○%で除して時価評価額に還元する方法を行った。)
平成○○年度建物等期末帳簿価額 ××××
減価償却不足累計額 ××××
差引建物等時価相当額 ×××× |
|
|
<貸借対照表様式例>(非出資商工組合を除く)
貸借対照表
平成 年 月 日
|
(資産の部)
I 流動資産
| 1 現金及び預金 |
××× |
| 2 受取手形 |
××× |
| 3 売掛金 |
××× |
| 4 未収金 |
××× |
| 5 貸付金 |
××× |
| 6 短期有価証券 |
××× |
| 7 棚卸資産 |
××× |
| 8 貸倒引当金 |
××× |
| 流動資産計 |
×××× |
II 固定資産
| i 有形固定資産 |
|
|
有形固定資産計
|
×××× |
| ii 無形固定資産 |
|
| 無形固定資産計 |
×××× |
| iii 外部出資その他の資産 |
|
外部出資その他の
資産計 |
×××× |
| 固定資産計 |
××××× |
III 繰延資産
|
(負債の部)
I 流動負債
| 1 支払手形 |
××× |
| 2 買掛金 |
××× |
| 3 未払金 |
××× |
| 4 短期借入金 |
××× |
| 5 転貸借入金 |
××× |
| 6 預り金 |
××× |
| 7 未払費用 |
××× |
| |
|
| 流動負債計 |
×××× |
II 固定負債
| 1 長期借入金 |
××× |
| 固定負債計 |
×××× |
| 負債合計 |
××××× |
(純資産の部)
I 組合員資本
| i 出資金 |
|
|
1 払込出資金
|
××× |
| 2 未払込出資金 |
△ ××× |
| 出資金計 |
×××× |
| ii 資本剰余金 |
|
| 1 資本準備金 |
|
| (1)加入金 |
×××× |
| 2 その他の資本剰余金 |
|
| (1)増口金 |
××× |
| (2)出資金減少差益 |
××× |
| 資本剰余金計 |
×××× |
| iii 利益剰余金 |
|
| 1 利益準備金 |
××× |
| 2 その他の利益剰余金 |
|
| (1)教育情報費用繰越金 |
|
| (2)特別積立金 |
××× |
(3)当期未処分剰余金
又は当期未処理損
失金 |
××× |
| 当期剰余金又は当期損失金 |
××× |
前期繰越剰余金
又は前期繰越損失金
|
××× |
| 利益剰余金計 |
×××× |
II 評価・換価差額等
1 その他有価証券
評価差額金 |
××× |
2 その他評価・
換価差額等 |
|
(1)脱退者持分払
戻勘定 |
××× |
| 評価・換価差額等計 |
××× |
| 純資産合計 |
×××× |
| 負債及び純資産合計 |
××××× |
| (3)当期未処分剰余金 |
|
|
(注)有形固定資産から直接控除を行っている金額。
減価償却累計額 ×××
減損損失累計額 ×××
|
|
<損益計算書様式例>(非出資商工組合を除く)
事業別損益計算書を必要としていない組合を対象にした様式例
損益計算書
自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
|
(事業費用の部)
I 販売事業費用
| 1 売上原価 |
|
| (1)期首棚卸高 |
×× |
|
| (2)当期仕入高 |
×× |
|
| (3)期末棚卸高 |
△ ×× |
×× |
| 2 販売費 |
|
II 購買事業費用
| 1 売上原価 |
|
| (1)期首棚卸高 |
×× |
|
| (2)当期仕入高 |
×× |
|
| (3)期末棚卸高 |
×× |
×× |
| 2 購買費 |
|
|
III 金融事業費用
IV 生産・加工事業費用
| 1 売上原価 |
|
| (1)期首棚卸高 |
×× |
|
| (2)当期製品製造原価 |
×× |
|
| (3)期末棚卸高 |
△ ×× |
×× |
| 2 生産・加工費 |
|
|
V 検査・試験・開発事業費用
| 1 検査費 |
|
×× |
| 2 試験研究費 |
|
×× |
| 3 研究開発費 |
|
×× |
| |
計 |
×× |
VI 教育情報事業費用
| 1 講習会費 |
|
×× |
| 2 視察費 |
|
×× |
| 3 情報提供費 |
|
×× |
| |
計 |
×× |
| |
|
|
|
(事業収益の部)
I 販売事業収益
| 1 売上高 |
|
| (1)外部売上高 |
×× |
|
| (2)組合員売上高 |
×× |
|
| (3)受取手数料 |
×× |
×× |
| |
|
II 購買事業収益
| 1 売上高 |
|
| (1)組合員売上高 |
×× |
|
| (2)外部売上高 |
×× |
|
| (3)受取手数料 |
×× |
×× |
| |
|
|
III 金融事業収益
IV 生産・加工事業費用
| 1 売上高 |
|
| (1)組合員売上高 |
×× |
|
| (2)外部売上高 |
×× |
|
| (3)受取手数料 |
×× |
×× |
| |
|
|
V 検査・試験・開発事業収入
| 1 受取検査料 |
|
×× |
| 2 受取試験料 |
|
×× |
| 3 試験開発負担金収入 |
|
×× |
| |
計 |
×× |
VI 教育情報事業収益
| 1 教育情報賦課金収入 |
|
×× |
2 仮受賦課金繰入
・戻入 |
|
×× |
3 教育情報費用
繰越金戻入 |
|
×× |
| 4 教育事業参加料収入 |
|
×× |
| |
計 |
×× |
|
|
VII 福利厚生事業費用
| 1 親睦会費 |
|
×× |
| 2 慶弔費 |
|
×× |
| |
計 |
×× |
| 事業収益の部合計 |
|
××× |
|
VII 福利厚生事業収益
|
|
(一般管理費の部)
VI 一般管理費
| 1 人件費 |
|
|
| 2 業務費 |
|
|
| 3 諸税負担金 |
|
|
| 一般管理費の部合計 |
|
×××× |
|
(賦課金等収入の部)
VI 賦課金等収入
1 賦課金収入
(平等割) |
|
×× |
2 賦課金収入
(差等割) |
|
×× |
| 3 特別賦課金等収入 |
|
×× |
| 賦課金等収入の部合計 |
|
××× |
|
|
(事業外費用の部)
VII 事業外費用
| 1 支払利息 |
|
×× |
| 2 手形売却損 |
|
×× |
| 事業外費用の部合計 |
|
××× |
(特別損失の部)
VIII 特別損失
| 1 固定資産売却損 |
|
×× |
| 2 固定資産除却損 |
|
×× |
| 特別損益の部合計 |
|
××× |
税引前当期純利益金額
又は税引前当期純損失金額 |
|
××× |
当期純利益金額又は
当期純損失金額 |
|
××× |
|
(事業外収益の部)
VII 事業外収益
| 1 受取利息 |
|
×× |
| 2 受取外部出資配当金 |
|
×× |
| 事業外収益の部合計 |
|
××× |
(特別利益の部)
VIII 特別利益
| 1 固定資産売却益 |
|
×× |
| 2 補助金収入 |
|
×× |
| 3 貸倒引当金戻入 |
|
×× |
| 特別利益の部合計 |
|
××× |
|
|
|
<剰余金処分案様式例>(非出資商工組合を除く)
剰余金処分案
自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
| I 当期未処分剰余金 |
|
|
| 1 当期純利益金額(又は当期純損失金額) |
×× |
|
| 2 前期繰越剰余金(又は当期繰越損失金) |
×× |
|
| II 組合積立金取崩額 |
|
|
| 1 会館建設積立金取崩額 |
×× |
|
| 2 特別積立金取崩額 |
×× |
××× |
| III 剰余金処分額 |
|
|
| 1 利益準備金 |
×× |
|
| 2 教育情報費用繰越金 |
×× |
|
| 3 組合積立金 |
|
|
| 特別積立金 |
×× |
|
| 4 出資配当金 |
×× |
|
| 5 利用分量配当金 |
×× |
××× |
| IV 次期繰越剰余金 |
|
××× |
(作成上の留意事項)
(1)出資商工組合、企業組合、協業組合は、教育情報費用繰越金の処分はない。
(2)脱退者への中協法20条による持分払戻があるときは、別に、脱退者持分払戻計算書を作成する。
|
|
<損失処理案様式例>(非出資商工組合を除く)
損失処理案
自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
| I 当期未処理損失金 |
|
|
| 1 当期純損失金額(又は当期純利益金額) |
×× |
|
| 2 前期繰越損失金(又は前期繰越剰余金) |
×× |
××× |
| II 損失てん補取崩額 |
|
|
| 1 組合積立金取崩額 |
|
|
| 特別積立金取崩額 |
×× |
×× |
|
| 2 利益準備金取崩額 |
×× |
|
| 3 資本剰余金取崩額 |
×× |
|
| 4 出資金減少差益取崩 |
×× |
××× |
| III 次期繰越損失金 |
|
×× |
(作成上の留意事項)
(1)中協法56条による出資一口の金額の減少を行い生じた出資金減少差益(定款参考例54条の減資差益)及び、持分計算の結果出資金に満たない額を払い戻した時に生じる出資金減少差益(定款参考例14条の減資差益)を、損失てん補に充てるときは、資本準備金取崩額に表示する。
(2)当期未処理損失額が少なく、次期以降の利益で、てん補できる見込みのときは、次期以降へ繰越損失金として繰越してもよい。
|
|
<事業報告書様式例>
(全組合共通)
事業報告書
自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
- 事業活動の概況に関する事項
- 事業年度末日における主要な事業内容・当該事業年度における事業の経過及びその成果(当該事業年度における主要な事業活動の内容・経過及び成果を事業ごとに記載)
(1)共同購買事業
①事業内容と経過の概要
②事業の成果
(2)○○事業
- 増資及び資金の借入れその他の資金調達の状況
|
資金実績表
自平成○年4月1日 至平成○年3月31日
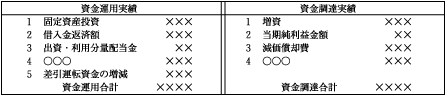
|
- 設備投資の状況(当該事業年度中に実施した設備投資の状況を記載)
①組合会館・組合事務所 各○箇所
②工場・倉庫 各○箇所
③駐車場 各○箇所
- 業務提携等重要事項の概要(業務上の提携、子会社にする会社の株式又は持分の取得、事業全部又は一部の譲渡又は譲受け・合併・その他の組織再編成があった場合には、その状況を記載)
- 直前3事業年度の財産及び損益の状況
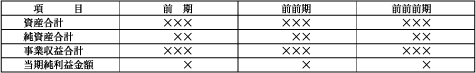
- 対処すべき重要な事項・組合の現況に関する重要な事項(対処すべき課題等、組合の現状に関する状況を記載)
- 運営組織の状況に関する事項
- 前事業年度における総会の開催状況(前事業年度中に開催した総会の状況(開催日時、出席組合員数、主な議案の議決状況)を記載)
- 組合員数及び出資口数の増減(出資口数の区分は適宜変更)

- 役員に関する事項
(1)役員の氏名及び職制上の地位及び担当
(2)兼務役員についての重要な事実(組合の役職以外に就いている外部会社等における役職、ただし員内役員については、組合にあっては組合員企業における役職、連合会にあっては会員組合における役職、所属員企業における役職を除く)
(3)辞任した役員の氏名
- 職員の状況及び業務運営組織図
(1)職員の状況
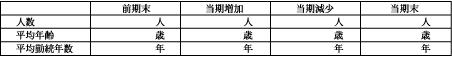
(2)組織図
(3)組合と協力関係にある組合員が構成する組織の概要
- 施設の設置状況(主たる事務所、柔たる事務所及び組合が所有する施設の種類ごとの主要な施設の名称及び所在地等)
- 組合の運営組織の状況に関する重要な事項
-
その他組合の状況に関する重要な事項
<監査報告書様式例>(全組合共通)
※省令の施行前に終了する事業年度に及び業務監査権限に関する経過措置の終了前に終了する事業年度に関する監事の権限は会計に関する監査に限定されていることから、事業報告書の監査に関する箇所は適用されない。
監査報告書
中小企業等協同組合法第40条第5項により、特定理事から受領した第○期財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案(損失処理案)及び事業報告書を監査した。
1.監査方法の概要
決算関係書類及び事業報告書の監査のため、会計に関する帳簿、書類を閲覧し、計算書類について検討を加え、必要な実査、立会、照合及び報告の聴取、理事会議事録の閲覧、重要な事業の経過報告の聴取その他通常とるべき必要な方法を用いて調査した。
2.監査結果の意見
(1)財産目録、貸借対照表、損益計算書は、組合の財産及び損益の状況のすべての重要な点において適正に表示している。
(2)剰余金処分案(損失処理案)は法令及び定款に適合している。
(3)事業報告書は、法令及び定款にしたがい、組合の状況を正しく示している。
3.追記情報(記載すべき事項がある場合)
平成○○年○月○日
○○組合
監事○○○○
(作成上の留意事項)
(1)監査権限限定組合(監事の監査の範囲が会計に関するものに限定されている組合)の監事は、事業報告書に関する記載を削除し、下記例のように事業報告書を監査する権限のないことを監査報告書の前文に追加記載する。
「なお、当組合の監事は、定款第○条(監事の職務)に定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告書を監査する権限を有していない。」
(2)「3.追記情報」は記載すべき事項がある場合に設け、正当な理由による会計方針の変更、重要な偶発事象、重要な後発事象その他の事項であって、監事の判断に関して説明を付す必要がある事項や決算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項を記載する。
(3)監査の日付は、特定理事に監査報告を通知した日を記載する。
(4)署名は、監事全員とする。
(5)商工組合(非出資商工組合を含む)の場合は、「中小企業等協同組合法第40条第5項により」の部分を「中小企業団体の組織に関する法律第47条第2項において準用する中小企業等協同組合法第40条第5項により」と書き換える。
|
軽微な規約等の変更の場合の総会議決の省略
規約等の設定、変更、廃止は総会の議決事項ですが、軽微な変更及び主務省令(施行規則)で定める変更事項に関しては、定款でその旨及び組合員への通知方法等を定めることにより、総会の議決を要しないこととすることができるようになりました。
〈定款参考例〉
(規約等)
第○条 この定款で定めるもののほか、必要な事項は、規約で定める。
- 規約及び共済規程の設定、変更又は廃止は総会の議決を経なければならない。
- 前項の規定にかかわらず、規約及び、共済規程の変更のうち軽微な事項並びに関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る)に伴う規定の整理及び責任共済等の事業についての共済規程の変更については、総会の議決を要しないものとする。この場合、総会の議決を要しない事項の範囲、変更の内容について、文書又は電磁的方法により通知するとともに、第○条の規定に基づき公告するものとする。
(注1)共済事業を実施しない場合は、見出しを「規約」に変更するとともに、第2項及び第3項中の「共済規程」「責任共済等の事業についての共済規程の変更」を削除すること。
(注2)第3項中の組合員に対する周知方法は、組合によって適宜、選択すること。
理事、監事ごとの役員報酬の設定
会社法の準用により、理事、監事の報酬の設定は、それぞれに区分し、総会の議決を経るか、定款へ記載することが必要となりました。
〈定款参考例〉
(理事及び監事の報酬)
第○条 役員に対する報酬は、理事と監事を区分して総会において定める。
(注1)理事と監事の報酬は総会において一括して定めず、理事と監事を区分して定めること。
(注2)理事、監事の報酬を定款に定めることもできる。
第○条 役員に対する報酬は、理事については総額○○円以内、監事については総額○○円以内とする。
共済事業に関する定義の創設
共済事業に関する定義が創設され、組合が行う福利厚生事業のうちで主務省令で定める一定の共済事業に対して諸規制が課されることとなりました。一定の共済金額を超えない共済事業については諸規制は課されませんが、一定の共済金額を超える場合には事業の名称等を問わず共済事業とみなされる場合がありますので注意が必要です。
II 大規模組合が対応しなければならない改正点(大規模組合改正点)
(3月号の6P「一般組合改正点」に追加して)
監事の権限拡大の義務化
監事の業務監査権限が義務となります
内容は「監事の権限拡大、監事の権限の会計監査への限定と組合員の権限拡大」で記載のとおり、大規模組合の監事には会計監査権限に加えて業務監査権限が与えられます。
員外監事選任の義務化
最低1名の員外監事を選出することが義務となります
事業年度開始の時に組合員数が1、000名を超える場合、監事のうち最低1名は組合員以外の者(員外監事)であることが必要となります。
これまでの員外監事とは異なった方々を選出する必要があります
これまでの員外監事の概念は、「組合員(個人事業者)または組合員たる法人(法人である組合員)の役員以外の者」であり、例えば、法人組合員の従業員は「員外監事」とされていました。
今回の改正により、大規模組合で選出しなければならないとされる員外監事は、「組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人」以外のものであって、かつ、就任前5年間に当該組合等の理事、使用人などでなかった者でなければならないとされており、これまでの員外監事や員外理事と概念が異なりますので留意する必要があります(大規模組合以外の組合で員外監事を選出することは、これまでどおり任意であり、その場合の員外監事の概念は従来どおりです)。
なお、この員外監事の設置義務には、経過措置が設けられており事業年度が4月に開始される組合の場合、平成20年4月以降に開催される平成19年度決算に関する通常総会終了以後に適用されますので、それまでに選出することが必要です。
ただし、経過措置期間中に員外監事を選出することは可能です。
法施行後、組合員数が「1,000人以下から新たに1,000人超になった場合」や「1,000人超から新たに1,000人以下になった場合」の対応は「監事の権限拡大、監事の権限の会計監査への限定と組合員の権限拡大」で、業務監査権限を付与された監事から会計監査限定の監事へ変更する場合等と同様の取扱いが規定されています。
〈定款参考例〉
(員外監事)
第○条 監事のうち1名以上は、組合員又は組合員たる法人の役員若しくは使用人以外の者で、就任前5年間に本組合の理事若しくは使用人又は本組合の子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、執行役員若しくは使用人でなかったものでなければならない。
(注1)組合員数が通常総会開催時点で1、000人を超える組合では、監事のうち、1人以上は員外監事を選任することが義務づけられており、この場合の員外監事の内容が法で限定されていることを前提とした規定である。したがって、組合員数が1、000人を超える可能性が低い場合は規定する必要はない。
(注2)員外役員を認めない組合にあっては本条を次のように記載すること。ただし、18ページ(注1)に留意すること。
(役員の要件)
第○条 本組合の役員は、組合員又は組合員たる法人の役員でなければならない。
余裕金運用の制限
余裕金の運用方法が制限されます
これまで資産の運用先については、火災共済協同組合・連合会及び自賠責共済を行う事業協同組合・連合会を除き、特段の制限がありませんでしたが、今後、組合員数1、000名を超える組合においては、資産の運用先に制限が設けられることとなっていますので留意する必要があります。
運用が可能なものとしては、預貯金、国債、地方債、一定の安全性が確保された有価証券とされており、具体的には省令等で規定されています。なお、行政庁の認可を受けた場合には、この運用制限以外での運用が可能となっています。
また、改正法経過措置により、平成19年4月1日の時点で保有している資産が、法令上認められない運用先であった場合であっても、3年間は保有し続けることが可能となっています。
共同出資会社などの株式を取得している場合の対応が必要です
中協法施行規則では、有価証券については、上場株式だけが運用先として規定されています。
したがって、例えば組合が全額出資した株式会社がある場合などは、この規定に抵触します。この場合、3年間の猶予期間の中で、行政庁の認可を事後的に受ける必要がある場合もあることに留意することが必要です。
その他
役員の組合に対する損害賠償責任の免除が理事会の決議で可能となります
役員の組合に対する損害賠償責任の免除については、これまでは総会における組合員全員の同意により免除できることとされていましたが、定款に記載することにより理事会の議決をもって免除することができることになりました。
また、員外役員に対する損害賠償責任の免除に関連して、定款に定めることを前提として、組合と個々の員外役員の間で責任限定契約(一般組合でも可)を締結することができるようになりました。
いずれも、定款にその旨の規定を置くことが効力発生の要件となっています。
監事の職務が会計に関する監査に限定されている組合には適用されません
なお、監事に業務監査権限を付与しない組合では、この理事会での損害賠償責任の免除の議決はできず、損害賠償責任の免除をするためには、総会の特別議決によらなければなりません。
〈定款参考例〉
(役員の責任免除)
第○条 本組合は、理事会の決議により、法第38条の2第9項において準用する会社法第426条第1項の規定により、法及び主務省令に定める限度において役員の責任を免除することができる。
(注)本規定は、監事に理事の業務監査権限を与えない組合は規定することができない。
(員外理事及び員外監事との責任限定契約)
第○条 本組合は、員外理事及び員外監事と法第38条の2第9項において準用する会社法第427条の規定に基づく責任限定契約を締結することができる。
- 前項に基づき締結される責任限定契約に記載することができる額は○○○円以内とする。
|