|
|
 |

|
 |
月刊中小企業レポート
| 更新日:2006/11/09 |
|
特集3 官公需適格組合制度と官公需施策
1.官公需適格組合
- ■官公需適格組合とは
- 官公需の受注に対して特に意欲的であり、かつ受注した契約は、十分に責任を持って履行できる経営基盤(組織体制、財務状況等)が整備されている組合であることを中小企業庁(関東経済産業局)が証明する制度である。事業協同組合、企業組合、協業組合等が対象となっている。
平成18年3月31日現在全国で887組合が官公需適格組合の証明を取得し、年々増加している。業種別には、
物品関係…繊維、家具、印刷、石油、事務用品、生コン他229組合
役務関係…設計、測量、自動車整備、運輸、建物サービス他376組合
工事関係…土木、建築、電気、管、造園、畳他282組合
であり、広範囲に及んでいる。
長野県内の官公需適格組合は6組合である。平成18年度内に2組合(工事ロと役務)の新規取得が見込まれている。
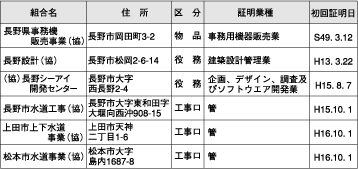
- ■官公需適格組合の種類
- 官公需適格組合の証明区分は「物品納入等」と「工事イ、ロ」の3種類である。同時に他の種類の証明を受けることはできない。
- 物品納入等(役務を含む)
- 工事イ(建設業許可が必要な工事を行う場合)
公共性のある工事であって、工事1件の請負代金の額が1、500万円以上のもの(電気工事、管工事、電気通信工事またはさく井工事にあっては500万円以上)を請け負うとする場合
- 工事ロ(建設業許可が不要な軽微な工事を行う場合)
- ■「物品納入等」(役務を含む)の証明基準
- 物品・役務で証明を取得しようとする場合は、定款に「共同受注事業」が規定されていることを前提に、以下の7つの基準を満たさなければならない。
- 組合の共同事業が組合員の協調裡に円滑に行われていること
- 官公需の受注について熱心な指導者がいること
- 常勤役職員が2名以上いること
- 共同受注委員会が設置されていること
- 役員と、共同受注した案件を担当した組合員が連帯責任を負うこと
- 検査員を置くなど検査体制が確立されていること
- 組合運営を円滑に遂行するに足りる経常的収入があること
長野県中小企業団体中央会(以下「中央会」という)における相談事例では③の基準を満たすことが困難なため申請を断念した事例が数多く見うけられる。
- ■「工事」の証明基準
- 物品納入等の基準に加えて、工事イの場合は以下の8、9、10の3つ、工事ロの場合は⑧の基準を満たさなければならない。
- 共同受注事業を1年以上行っており相当程度の受注実績があること
- 工事1件の請負代金の額が1、500万円(電気、管工事等は500万円)以上のものを受注しようとする組合は、常勤役員が1名以上、常勤職員が2名以上おり、その役職員のうち2名は受注しようとする工事の技術者であること(工事イ)
- 総合的な企画及び調整を行う企画・調整委員会が現場ごとに設置され、工事全体が契約通りに施工される体制が整備されていること(工事イ)
- ■発注機関は官公需適格組合に安心して仕事をまかせることができる
- 官公需適格組合は、受注した契約に対して十分に責任を持って履行できる経営基盤(組織体制、財務状況等)が整備されている組合であることを中小企業庁(=国)が認める制度なので、発注機関は安心して仕事をまかせることできる。証明基準の⑤は、担当した組合員に万が一事故ある時は他の組合員がその仕事を引き継ぐなどして組合全体で責任を負うことを求めているのである。
-
- ■官公需適格組合の証明取得は簡単ではない
- 官公需適格組合の証明を取得するためには、前述の基準を満たした上で、定款の変更、総会における官公需共同受注規約等の規約の議決、申請書に加えて何種類もの添付書類の作成等、特に初回の申請時には相当のパワーが必要となる。更に、2年に一度の継続更新(物品納入等の一部の場合のみ3年)、中間の1年目には中間報告の提出が求められている。
このように新規取得、継続更新とも簡単ではないが、中央会には証明取得のためのノウハウが蓄積されているので、相談されたい。
-
-
- ■官公需適格組合といえども営業努力は必要だ
- このような苦労を重ねて証明を取得しても地道な営業努力無くして官公需の共同受注は増加しない。
全国中小企業団体中央会の官公需適格組合実態調査結果(平成18年6月1日現在で全国の官公需適格組合を対象に実施)によれば、組合の役員による挨拶回りや陳情、共同受注委員会や担当者による窓口訪問、ホームページ・広報誌・パンフレット・DVD等による組合紹介により一定の成果を上げている。また、組合独自の技術力、緊急修繕や小工事への迅速な対応、ISO14001やエコアクション21の取得等による発注機関へのアピールを行っていることが分かった。
-
-
- ■官公需適格組合の特例
- 国等の競争参加資格審査において官公需適格組合には「総合点数の算定特例」が認められている。これは、組合の総合点数の算定にあたり、一定の条件を満たす組合員の点数を組合の点数に加算できる制度である。県はこの制度が有効である。一方、県内市町村はこの制度を採用していないところが大多数と推測される。
官公需適格組合はこの制度を活用することで、より規模が大きな発注案件に応札できることになる。中央会は、県内市町村に対して、本制度の採用を求めるものである。
-
-
- ■官公需適格組合の課題と克服策の一提案
- 昨今は競争性・透明性を担保するために、随意契約から指名競争入札へ、指名競争入札から一般競争入札へと入札制度の改革が進んでいる。官公需適格組合といえども一応札者に過ぎなくなっている。このような状況ではせっかくの制度が効果を発揮しない。
指名競争入札において、官公需適格組合をはじめとする事業協同組合等が応札する場合、組合員との同時応札が認められていないために、その地域内の有資格応札者が少なくなり、地域外からの応札者を認めざるを得ないとの指摘がある。この指摘に対して、組合が応札する場合一応札者とカウントするのではなく、全組合員数または入札参加資格を持つ組合員数の応札者があったと見なすことができないであろうか。例えばある組合で入札参加資格を持つ組合員が10社あったとすれば10社が応札したと見なすのである。
一般競争入札においては、受注希望型競争入札や総合評価落札制度などのいずれの場合でも、官公需適格組合には一定の点数加算を行うこととする。こうすることで、価格のみの競争をさけ、官公需適格組合はある程度の優位性を保てるので単なる一応札者ではなくなると思われる。
2.官公需施策
中央会は官公需発注・落札情報の提供をはじめとして、官公需適格組合等がより多くの官公需の確保をできるようにするための事業を行っている。この中から平成18年度に実施したいくつかの事業を紹介する。
- ■官公需確保対策地方推進協議会の開催協力
- 官公需受注確保を目的に、関東経済産業局の主催により発注者側と受注者側の出席を得て年1回開催している。本年度は、平成18年9月11日(月)に長野市「ホテル信濃路」にて、57名の参加を得て開催された。
関東経済産業局より平成18年度の中小企業者に関する国等の契約の方針(以下「国等の契約の方針」という)について、長野県より官公需確保対策について説明を受けた後、中央会の官公需関連事業について説明を行った。
平成18年度の国等の中小企業向け契約の目標は、約3兆9、346億円。官公需総予算に占める比率は47・9%である。平成17年度は、約4兆1、286億円、46・9%であったので、総額が減少し比率が増えたことになる。
国等の契約の方針のポイントは、技術力のあるベンチャーに対する調達改善である。国の全省庁統一参加資格制度において、技術力のある中小企業者に対して、特許保有件数等の技術力を加味して上位等級への入札参加が認められていたが、平成17年度までは、精密機器等物品の製造5分野に限定されていた。平成18年度はこれを全ての物品の製造、役務の提供に拡大した。
質疑の内容は次のとおりである。
官公需適格組合のメリットについての質問に対して、工事の特例措置などがあるとの回答がされた。
国等の契約の方針から随意契約が無くなったことについての質問に対しては、公益法人等で随意契約が多く国会で問題になった。少額随意契約の制度は廃止されたわけではないが、あくまでも国等の契約は一般競争が基本であるとの回答がされた。

平成18年度官公需確保対策地方推進協議会
-
- ■官公需問題懇談会の開催
- 官公需受注上の問題点を把握しその具体的解決策を探るために、発注者側と受注者側の出席を得て年1回開催している。
本年度は、官公需確保対策地方推進協議会と同日に同じ場所で時間をずらして開催した。発注機関13名、組合関係者33名、事務局9名の参加があった。
最初に、長野県土木部の専門指導員より、受注希望型競争入札は地元の意欲のある企業に対し、地元貢献度(ボランティア)、除雪などで点数加算されること、総合評価落札制度は100点満点で価格、技術力、施工方法・施工能力、社会的貢献度(ボランティア、除雪)等を加算する方式(国交省は除算方式)であること等の説明を受けた。
その後、事務局より官公需共同受注組合アンケート調査結果の報告(後述)を行ったあと会員懇談に入った。
①除雪、ボランティアで日頃地域貢献活動を行っているので、その点を加味して随意契約での契約をお願いしたい。②受注希望型競争入札に参加する用件を教えて欲しい。③組合と組合員が同じ入札に同時に参加できるのか。④公共工事(解体)の入札について、産業廃棄物中間処理の資格業者(破砕施設の有無だけ)に入札許可を出しているが、実際は、最終処分の能力がある業者にのみ許可すべきではないのか等、多くの質問が出された。
最後に、長野県官公需組合協議会の佐藤会長(長野設計(協)理事長)から、「国の方針では中小企業組合の受注機会の増大がうたわれているが、現実にはただの大型JVとしか見られていない。各組合の受注アップを図る必要がある。発注機関の皆さんには各組合の入札を図り、特に、適格組合には優秀な組合員が集まっているので、官公需法の趣旨に即して入札機会を作って欲しい。」との要請をして懇談会を終了した。

平成18年度官公需問題懇談会

平成18年度官公需問題懇談会
- ■官公需資料作成提供事業
- 国の出先機関、県、市町村の発注情報、落札情報及び入札参加資格登録申請手続き情報を年3回郵送により収集し、冊子を印刷して組合等へ提供している。発注情報については年3回の定期的な収集だけでなく、随時収集して該当する組合等へ提供している。
本年度より町村を収集先に追加した。そして官公需に関係深い組合等へ第1回目の収集結果を冊子にして配布した。
この事業については、発注機関がホームページで情報を公開するようになっていることから、事業の必要性や方法について改善が求められている。そこで冊子の配布に合わせてアンケートを実施し、来年度以降、必要に応じた見直しを行う。
-
-
- ■官公需情報ホームページの充実
- 中央会はホームページを通じて官公需情報を適宜提供している。官公需適格組合制度の紹介、官公需資料作成提供事業で作成した官公需情報の公開、国が毎年発表する中小企業者に関する国等の契約の方針、発注機関へのリンク集、官公需に係わる法律などを掲載してあるので、是非ともアクセスしていただきたい。
「http://www.alps.or.jp/chuokai/kankoju/」
3.官公需共同受注組合調査結果
官公需関連組合228組合を対象とし、平成18年8月17日に郵送により調査を実施した。回収は52組合、回収率は22.8%。ここではその結果の一部を紹介する。
(1) 官公需共同受注の実績
「ある」が18組合(35.3%)、「無い」が33組合(64.7%)。(無回答1組合)
受注があると回答された組合の、官公需共同受注の平均は2,880万円(最大 12,000万円、最小47万円)である。その分野は物品が3組合、役務が9組合、工事が6組合である。
(2) 官公需共同受注事業の実施にあたり組合で行っていること
(複数回答)
地域貢献活動が多く、定期的な技術研修や発注機関のホームページ閲覧が続いている。
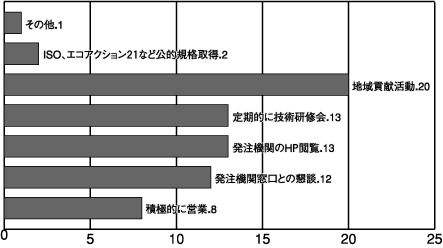
(3)官公需共同受注実施上の課題
(複数回答)
発注案件・金額の減少、低価格落札の横行が上位となった。
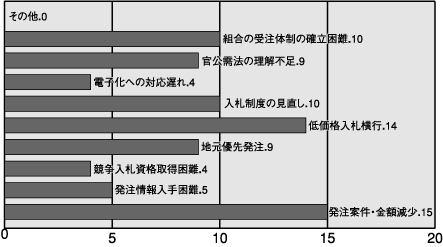
官公需のことは中央会へご相談ください!!
編集 連携支援部
|
 |

|