|
特集 よくわかる中小企業のための新会社法33問33答その2(抜粋)
平成17年6月29日、第162回国会で「会社法」(以下、「新会社法」)が成立しました。
これまで、会社に関する規定は、商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(いわゆる「商法特例法」)など、様々な法律に分散しており、一つの法律にまとまっていませんでした。
新会社法で導入される制度のうち特に中小企業にとってメリットが大きいと考えられるものについて、内容がよくわかるよう、33の問答形式にまとめたものが中小企業庁発行の『よくわかる中小企業のための新会社法33問33答』です。
先月号に引き続き抜粋したものを掲載いたします。
なお、この『よくわかる中小企業のための新会社法33問33答』の詳細は中小企業庁のホームページでも、ご覧いただけます。
組織再編をスムーズに、スピーディーに!
合併等の対価の柔軟化
 17.「合併等の対価の柔軟化」とは何ですか。 17.「合併等の対価の柔軟化」とは何ですか。
 会社が合併等を行う場合に、相手会社の株主に対して交付する財産(対価)の種類が柔軟に認められるようになったことです。 会社が合併等を行う場合に、相手会社の株主に対して交付する財産(対価)の種類が柔軟に認められるようになったことです。
注意:
「合併等の対価の柔軟化」に関する規定は、企業が敵対的買収に対する防衛策を準備する期間を設けるため、新会社法の施行日からさらに1年間は施行されないこととなっています。
■合併等の対価の柔軟化
▼新会社法
合併等の際、消滅会社等の株主に対して、現金や親会社の株式等、存続会社等の株式以外の財産を交付できることになった。
ただし、施行は、新会社法本体の施行日から1年後。
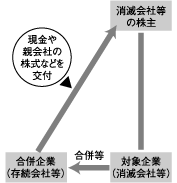
- 経営陣の同意(合併契約の調印)。
- 双方の会社で株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)。
- 消滅会社等が株式譲渡制限会社(Q1参照)以外の会社であり、かつ合併の対価に流動性の低い株式を活用する場合には、さらに消滅会社等の特殊決議(議決権を有する株主の過半数、かつ当該株主の議決権の2/3以上の賛成)が必要。
簡易組織再編の範囲拡大
 18.簡易組織再編は、どう変わりますか。 18.簡易組織再編は、どう変わりますか。
 簡易組織再編の規模の要件が5%から20%へ拡大されます。 簡易組織再編の規模の要件が5%から20%へ拡大されます。
■簡易組織再編を行うに当たって
- ①適用要件の緩和
- 合併等の際には、存続会社等が消滅会社等の株主に対価として交付する株式その他の財産額が存続会社等の純資産額の20%以下である場合に、簡易組織再編制度を利用することができるようになります(改正前は5%以下)。
- ②株式譲渡制限会社における注意点
- 株式譲渡制限会社(Q1参照)がその株式の発行・移転を伴う組織再編を行う場合は、簡易組織再編制度は利用できません。
■簡易組織再編の範囲拡大
▼これまで
原則として、会社が合併等の組織再編を行う場合には、双方の会社の株主総会での特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)が必要。
例外として、組織再編を行う存続会社等の交付する株式の総数が発行済株式総数の5%以下であれば、存続会社等は取締役会の決議のみで合併等ができる(産業再生法で右記の特例あり)。
▼新会社法
20%に拡大!
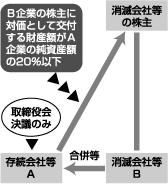
略式組織再編の導入
略式組織再編とは、どのような制度ですか。
支配関係にある会社間での組織再編について、被支配会社での株主総会決議を不要とする制度です。
■略式組織再編を行うに当たって
- 1.議決権の要件
- 親会社(支配会社)が議決権の90%以上を保有している子会社(被支配会社)の組織再編を行う際に、被支配会社での株主総会が不要となる略式組織再編制度を利用することができます。
- 2.株式譲渡制限会社における注意点
- 株式譲渡制限会社(Q1参照)がその株式の発行・移転を伴う組織再編を行う場合は、略式組織再編を利用できません。
- 3.少数株主の保護規定
- 被支配会社の株主は、略式組織再編行為が法令・定款違反、または不当な条件で行われることにより、不利益を受けるおそれがある場合には、その略式組織再編行為の差止め請求を行うことができます。
■略式組織再編の導入
▼これまで
略式組織再編制度なし(産業再生法では特例あり)。
▼新会社法
完全な支配関係に近い会社(議決権の90%以上保有)間の組織再編の場合、被支配会社の株主総会決議を不要とする。
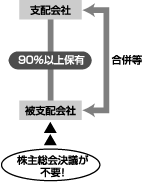
これまでの有限会社や合名会社・合資会社はどうなる?
有限会社制度の廃止
 20.有限会社制度が廃止されるそうですが、既存の有限会社はどうなるのですか。 20.有限会社制度が廃止されるそうですが、既存の有限会社はどうなるのですか。
 特例有限会社制度により、新会社法施行後も有限会社の商号をそのまま使用することが認められます。株式会社の商号を使用する通常の株式会社に移行することももちろん可能です。 特例有限会社制度により、新会社法施行後も有限会社の商号をそのまま使用することが認められます。株式会社の商号を使用する通常の株式会社に移行することももちろん可能です。
■有限会社の新設はできなくなる
注意:
新会社法施行後に会社を設立する場合は、特例有限会社制度は適用されないため、有限会社を新設することはできなくなります。
*いつでも通常の株式会社へ移行することが可能!
特例有限会社
 21.特例有限会社となるためには、何か手続が必要ですか。 21.特例有限会社となるためには、何か手続が必要ですか。
 特例有限会社となるために特段の手続等は必要なく、存続期間の制限もありません。 特例有限会社となるために特段の手続等は必要なく、存続期間の制限もありません。
■特例有限会社の規制
特例有限会社には、基本的にこれまでの有限会社と同じ規制が適用されますが、一部次のような相違点があります。
- これまで50名とされてきた社員の員数制限が廃止。最低資本金制度も撤廃。
- 新株予約権や社債の発行が可能に。
*特例有限会社として存続するのに、特別な手続は不要!
【お役立ち情報】
特例有限会社の法的位置付け
特例有限会社は、会社法上は株式会社となり、経過措置で「有限会社」の商号の継続使用や従前の規律の維持が認められるという位置付けになります。新会社法施行後は、「有限会社の定款」は「株式会社の定款」に、「社員」は「株主」に、「持分や出資口数」は「株式や株式数」と読み替えられることになります。
通常の株式会社への移行
 22.特例有限会社から通常の株式会社に移行するには、どのような手続が必要ですか。 22.特例有限会社から通常の株式会社に移行するには、どのような手続が必要ですか。
 定款における株式会社への商号変更、特例有限会社の解散登記および株式会社の設立登記を行う必要があります。 定款における株式会社への商号変更、特例有限会社の解散登記および株式会社の設立登記を行う必要があります。
■特例有限会社から通常の株式会社への移行手続
特例有限会社から通常の株式会社(注)へ移行するには、次の手続が必要になります。
- 商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更の株主総会決議
- 特例有限会社についての解散の登記および商号変更後の株式会社についての設立の登記
(注)特例有限会社は、会社法上は株式会社の一種となるので、ここでは特例有限会社以外の株式会社を「通常の株式会社」と呼んでいます。右記の手続は組織変更(会社類型の変更)ではなく、商号変更となります。
*特例有限会社から通常の株式会社への移行は、商号変更と登記だけで簡単にできる!
【お役立ち情報】
通常の株式会社への移行コスト
右記手続を行うに当たって必要となる登録免許税は次のとおりです。
解散の登記:3万円、設立の登記:資本金額の1,000分の1.5(税額が3万円未満のときは3万円)
特例有限会社と株式譲渡制限会社は、それぞれ次のような特徴があります。
- 特例有限会社のまま存続するメリット
*取締役、監査役の任期に制限がない(Q4参照)。
*決算公告義務がない(Q16参照)。
*慣れ親しんだ商号を引き続き使用でき、商号変更に伴うコスト(名刺・看板・ハンコの変更費用等)も不要。
- 株式譲渡制限会社へ移行するメリット
*対外的信頼性の向上が期待できる。
*会計参与(Q14参照)、会計監査人を設置できる。
株式会社制度と有限会社制度の統合
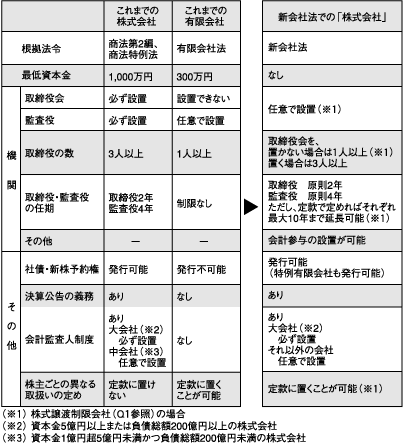
合名会社・合資会社から株式会社への組織変更
 23.合名会社・合資会社を株式会社に変更することは可能ですか。 23.合名会社・合資会社を株式会社に変更することは可能ですか。
 合名会社・合資会社から株式会社へ組織変更することができるようになります。 合名会社・合資会社から株式会社へ組織変更することができるようになります。
■株式会社への移行が簡単に
合名会社・合資会社から株式会社への組織変更が認められることで、次のようなメリットが考えられます。
*別途株式会社を設立して合併や営業譲渡を行う必要がない。
*業の許認可(酒類販売等)の再取得などの手間とコストが不要。
組織変更の具体的な手続は次のとおりです。
- 組織変更計画の作成(定款で定める事項の決定、効力発生日の決定等)。
- 組織変更計画についての総社員の同意。
- 官報公告・債権者への催告を行い、異議を申し立てた債権者への弁済措置。
一人合名会社、法人無限責任社員
 24.合名会社・合資会社の社員の規定は、どう変わりますか。 24.合名会社・合資会社の社員の規定は、どう変わりますか。
 社員1名のみの合名会社の設立・存続ができるようになるほか、法人が無限責任社員になることが認められます。 社員1名のみの合名会社の設立・存続ができるようになるほか、法人が無限責任社員になることが認められます。
*一人合名会社、法人無限責任社員の導入で、合名・合資会社の設立・存続が容易に!
創業をスムーズにする制度へ
会社設立手続の簡素化
 25.会社の設立手続はどのように簡素化されますか。 25.会社の設立手続はどのように簡素化されますか。
 最低資本金制度の撤廃、類似商号規制の廃止、払込金保管証明制度の一部廃止等を含め、設立手続の簡素化が図られています。 最低資本金制度の撤廃、類似商号規制の廃止、払込金保管証明制度の一部廃止等を含め、設立手続の簡素化が図られています。
■会社設立手続はこう変わる
新会社法で簡素化された主な手続には、次のようなものがあります。
- 最低資本金制度の撤廃(Q26~28参照)
株式会社1,000万円、有限会社300万円の最低資本金制度は、創業促進の観点から撤廃されます。
- 類似商号規制の廃止(Q29参照)
商業登記手続のうち、企業活動の広範化や登記手続の簡素化の要請により類似商号規制が廃止され、同時に類似の判断基準になっていた「会社の目的」についても記載基準が緩和されます。
- 払込金保管証明制度の一部廃止(Q30参照)
発起設立により会社を設立する場合、資本金の払込みについては、銀行等による保管証明書を不要とし、代わりに残高証明によれば足りるものとされます。
手続の簡素化に伴い、会社設立費用も大幅に削減されます(「お役立ち情報」参照)。
【お役立ち情報】
株式会社設立のフローチャート
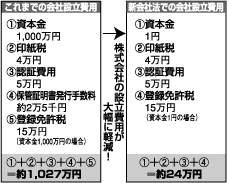
最低資本金制度の撤廃
 26.株式会社を設立するためには資本金はどれくらい必要ですか。 26.株式会社を設立するためには資本金はどれくらい必要ですか。
 最低資本金制度が撤廃され、資本金が1円でも会社を設立することができます。 最低資本金制度が撤廃され、資本金が1円でも会社を設立することができます。
■債権者保護の手段
新会社法では、会社の財産状況の適切な開示のため、次のような措置が講じられています。
*会計参与制度の導入(Q14参照)。
*すべての機関設計の株式会社に対する決算公告の義務付け(Q16参照)。
会社の実質的な資本充実を担保するため、次のような行為が禁止されています(Q15参照)。
*純資産額が300万円を下回る場合の剰余金の配当。
*分配可能額を超えた配当。
既存の「確認会社」(1円会社)の扱い
 27.最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」はどうなりますか。 27.最低資本金規制特例制度を利用した「確認会社」はどうなりますか。
 新会社法施行後、既存の「確認会社」は、5年以内に資本金を積み増す必要はなく、毎年行っていた経済産業大臣への書類提出も不要となります。 新会社法施行後、既存の「確認会社」は、5年以内に資本金を積み増す必要はなく、毎年行っていた経済産業大臣への書類提出も不要となります。
■「確認会社」は定款変更が必要
最低資本金規制特例制度によって設立された「確認会社」は、新会社法の施行により、
- 5年以内に最低資本金以上の増資を行わなくても解散不要。
- 毎年経済産業大臣に行っていた計算書類提出不要。
注意:
となるなど、これまでの義務がなくなります。 「確認会社」の定款には、「設立から5年以内に資本金を1,000万円(有限会社は300万円)に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが置かれているので、新会社法施行後にこの定めを削除する定款変更を行い、登記することが必要になります。
*「確認会社」は、5年以内の増資が不要に!
*新会社法施行後に定款変更が必要!
既存会社の資本金の減少
 28.既存の株式会社・有限会社が、資本金をこれまでの最低資本金の額未満まで減少させることも可能でしょうか。 28.既存の株式会社・有限会社が、資本金をこれまでの最低資本金の額未満まで減少させることも可能でしょうか。
 最低資本金制度が撤廃されるので、既存の株式会社・有限会社も無制限に資本金を減少させることが可能となります。 最低資本金制度が撤廃されるので、既存の株式会社・有限会社も無制限に資本金を減少させることが可能となります。
■減資の手続
新会社法では、従来の最低資本金制度が撤廃されます。これは、新設される株式会社だけに適用されるものではなく、新会社法施行前に設立された株式会社・有限会社も、減資の手続により無制限に資本金を減少させることが可能です。
資本金の額の減少は、原則として株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)を必要としますが、次の要件に該当する場合には、普通決議によることができます。
*定時株主総会の決議であること。
* 減資額がすべて欠損てん補にあてられること(注)。
(注)欠損てん補とは、資本金や準備金の減少により、欠損金(税法上の所得金額の計算上、損金が益金を超える部分の金額)を充当することです。資本金の減少により、剰余金がプラスになり、分配可能額(Q15参照)が生じるような場合は、原則どおり特別決議が必要となります。
商業登記制度の柔軟化
 29.商業登記制度は、どう変わりますか。 29.商業登記制度は、どう変わりますか。
 類似商号規制が廃止され、「目的」についての柔軟な記載ができるようになります。 類似商号規制が廃止され、「目的」についての柔軟な記載ができるようになります。
払込金保管証明制度の一部廃止
 30.払込金保管証明制度は、どう変わりますか。 30.払込金保管証明制度は、どう変わりますか。
 発起設立により会社を設立する場合は、「払込金保管証明」は必要なく、銀行の残高証明で足りることとなります。 発起設立により会社を設立する場合は、「払込金保管証明」は必要なく、銀行の残高証明で足りることとなります。
■発起設立と募集設立
株式会社の設立には、次の2通りの方法があります(実務上は発起設立の方法が多い)。
- 発起設立:
設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法。
- 募集設立:
発起人は設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、残りは他の株主を募集する方法。
新会社法では、発起設立については「払込金保管証明」が不要となり、「残高証明」で足りることとなります。また、一度払込みがなされれば、設立登記前でも払込金の引出しができるようになります。
注意:
募集設立の場合は、株式申込人の保護のため、これまでどおり「払込金保管証明」が必要とされます。
現物出資・事後設立の簡素化
 31.現物出資や事後設立は、どう変わりますか。 31.現物出資や事後設立は、どう変わりますか。
 現物出資する財産額が500万円以下の場合は、検査役の調査が不要となります。また、事後設立の場合の検査役調査も廃止されます。 現物出資する財産額が500万円以下の場合は、検査役の調査が不要となります。また、事後設立の場合の検査役調査も廃止されます。
合同会社(日本版LLC)の新設
 32.合同会社(日本版LLC)とは、どのような会社類型ですか。 32.合同会社(日本版LLC)とは、どのような会社類型ですか。
 合同会社は、有限責任社員のみで構成され、かつ組織の内部自治を認める新たな会社類型で、LLPとともに、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。 合同会社は、有限責任社員のみで構成され、かつ組織の内部自治を認める新たな会社類型で、LLPとともに、創業やジョイントベンチャーなどでの活用が期待されています。
■合同会社の特徴
合同会社は、次のような特徴を持っています。
- 有限責任制
合名会社や合資会社と違い、社員(出資者)は出資額の範囲までしか責任を負いません。
- 内部自治原則
株式会社と違い、利益や権限の配分が出資金額の比率に拘束されません。
また、取締役会や監査役のような機関を設置する必要がありません。
- 社員数
社員1名のみの合同会社の設立・存続が認められます。
- 意思決定
社員の入社、持分の譲渡、会社成立後の定款変更は、原則として社員全員の同意によります。
- 業務執行
各社員が原則として業務執行権限を有しますが、定款で一部の社員のみを業務執行社員と定めることも可能です。
- 決算書の作成
貸借対照表、損益計算書、社員特分変動計算書の作成が必要です。
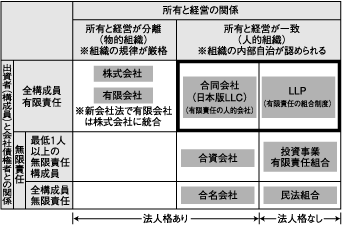
*合同会社(日本版LLC)は、「有限責任」「内部自治」の新しい会社類型!
*合同会社やLLPは、創業のコストも少額で済む!
*合同会社やLLPは、専門人材の集合体、ジョイントベンチャー、中小企業の連携などに活用できる!
|