|
中央会インフォメーション
事業主の皆様へ
65歳まで継続雇用をしましょう!!
高い就労意欲を有する高齢者が、長年培ってきた知識と経験を活かして、活き活きと活躍し続けることができる社会を築いていくために、65歳以上まで雇用する制度を導入しましょう。
経営者の皆様。高齢者雇用の推進は、“企業にとってメリット”のあることです。
◎人事労務管理の進展に寄与します。
| ・ |
経験豊富な人材を、低コストで雇用することも可能です(短期的な利点) |
| ・ |
年齢によらず個人の能力や成果を基準に処遇していくことで、企業の競争力が高まります(長期的な利点) |
| ・ |
若年労働者や中堅層のモラル向上や“やる気”を引き出します |
| ・ |
従業員が年金支給開始年齢の65歳まで安心して働くことができます |
| ・ |
65歳まで働くことを前提とした能力開発、キャリア形成を従業員に考えさせ、自己啓発に取り組ませるきっかけとなります |
| ・ |
そのことは、職場の活力と企業の競争力アップにつながります |
雇用延長等には助成金があります!!
高齢者の雇用を行う事業主への援助として、以下の助成金制度があります

| ① |
継続雇用定着促進助成金(継続雇用を図る労働者のために) |
| ② |
在職者求職活動支援助成金(高年齢者等への再就職援助を実施した事業主の方へ) |
| ③ |
移動高年齢者等雇用安定助成金(企業グループ内の中高年齢者を受け入れた事業主の方へ) |
| ④ |
特定求職者雇用開発助成金(高齢者をハローワーク(公共職業安定所)の紹介で雇い入れた事業主の方へ)
◇詳細は長野県雇用開発協会(TEL. 026-226-4684)へ |
【達成プランあれこれ】
| ・ |
定年年齢を60歳から65歳に一気に延長する(定年延長) |
| ・ |
厚生年金の支給開始年齢に合わせて、毎年1歳ずつ定年を引き上げる(定年延長) |
| ・ |
従業員が定年年齢を60歳か、65歳か選べるようにする(選択定年制) |
| ・ |
定年年齢に到達した者を退職させることなく引き続き雇用する(勤務延長制度) |
| ・ |
定年で一回退職させ、希望者は翌日から1年契約の嘱託として雇用(再雇用制度) |
| ・ |
希望者全員に定年後の仕事を提示、条件が合えば再雇用する(希望者全員の再雇用) |
| ・ |
高齢者派遣会社を作って定年者を雇用、元の職場に派遣する(高齢者派遣会社) |
65歳継続雇用についてのお問い合わせは
長野労働局職業安定課(026-226-0865)まで |

| ※ |
長野県中小企業団体中央会では厚生労働省から委託を受け「65歳継続雇用達成事業」を実施しております。
長野県中小企業団体中央会のホームページにもこの事業内容が掲載されておりますのでご覧下さい。 |
長野県最低賃金改正のお知らせ
長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」が改正され、平成17年10月1日
から適用されます。
最低賃金は、法律に基づき、地方最低賃金審議会の答申を受け、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、それ以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは、含まれません。
お問い合わせは
長野労働局 労働基準部賃金室(TEL.026-223-0555)
または最寄り労働基準監督署まで |
「仕事と家庭を考えるセミナー」開催のお知らせ
厚生労働省では毎年10月を「仕事と家庭を考える月間」として各種の啓発活動を展開中です。
長野労働局では10月21日(金)に松本市「ウエルサンピア松本」(松本市村井町)において「仕事と家庭を考えるセミナー」
を開催いたします。
セミナー内容等
| 開催日 |
平成17年10月21日(金)午後1時30分~午後4時 |
| 講 演 |
「資生堂のワーク・ライフ・バランス支援の取組み」 |
| 講 師 |
(株)資生堂CSR部次長 山極 清子氏
※その他 シナノケンシ(株)による事例発表 |
◎問い合わせ、申し込みは
21世紀職業財団長野事務所まで(TEL.026-223-4524) |
“中小企業の会計に関する指針”を公表(企業会計基準委員会ほか)
日本公認会計士協会・日本税理士会連合会・日本商工会議所及び企業会計基準委員会は、8月3日、「中小企業の会計に関する指針を」公表した。
同指針は、同4団体、学識経験者並びに中小企業庁、法務省及び金融庁が参加して「中小企業の会計の統合に向けた検討委員会」を設置し、(1)中小企業が計算書類を作成するに当たって拠ることが望ましい会計処理、(2)会計参与設置会社が計算書類を作成するに当たり拠ることが適当な会計処理、を示す指針について検討した結果を取りまとめたものである。
中小企業の会計に関する指針の詳細は下記のホームページをご覧下さい。
企業会計基準委員会ホームページ
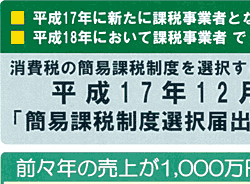 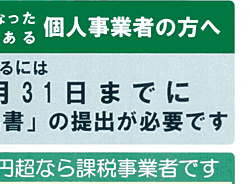
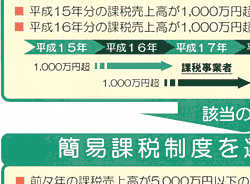 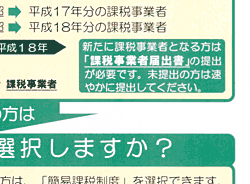
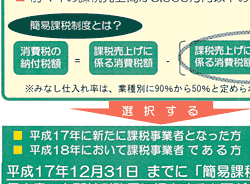 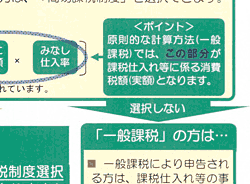
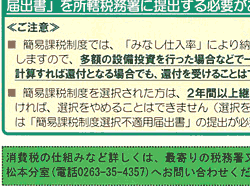 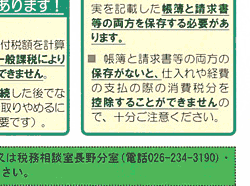
|