|
特集1 外国人研修生受入制度と中小企業
我が国では国際貢献の一環として、中国およびアジア諸国からの研修生・技能実習生の受け入れ制度を推進しています。制度運用の中核的機関である(財)国際研修協力機構(JITCO)によれば、発足以来13年間で受け入れた研修生は約30万人、技能実習生は約14万人と着実に成果を上げています。
本年10月、中央会が事務局となり「長野県外国人研修生受入団体連絡協議会」を設立し、外国人研修・技能実習制度の円滑な実施のための情報交換や、諸問題の解決を図っていく取り組みを始めました。
本特集では、制度の概要、外国人研修生・技能実習生の受け入れ状況、協同組合等における受入数の推移等について解説。さらに、長野県内での研修生・技能実習生受け入れを目的とした組合の設立状況および受け入れ状況と、その事業事例についてご紹介します。
外国人研修制度のあらまし
開発途上国等には、自国の経済発展と産業振興の担い手となる人材を育成する観点から、特に青壮年の働き手に先進国の進んだ技術・技能や知識を修得させようとするニーズがあります。このようなニーズに的確に応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間日本の産業界に受け入れて産業上の技術・技能・知識を修得してもらう仕組みが、「外国人研修・技能実習制度」です。
この制度は、研修生・技能実習生への技術・技能移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、日本の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
1.外国人研修制度の具体的な仕組み
●研修生要件
研修生は、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する者です。
| (1) |
いずれの研修形態にも共通の研修生要件
次の①②③のいずれにも該当する者
| ① |
18歳以上の外国人 |
| ② |
研修修了後母国へ帰り、日本で修得した技術・技能を活かせる業務に就く予定がある者 |
| ③ |
母国での修得が困難な技術・技能を修得するため、日本で研修を受ける必要がある者 |
|
| (2) |
研修形態による個別の研修生要件 |

| ■ |
団体監理型研修の受入れの場合(受入れ団体がそのメンバーである企業等と協力して行う研修生の受入れ)
次の①②のいずれにも該当する者
| ① |
現地国の国・地方公共団体からの推薦を受けた者 |
| ② |
日本で受ける研修と同種の業務に従事した経験がある者 |
|
●研修生を受け入れることのできる受入れ機関
団体監理型研修の受入れの場合
日本の公的な援助・指導を受けた商工会議所・商工会、事業協同組合等の中小企業団体、公益法人などが受入れの責任を持ち、その指導・監督の下に研修生を受け入れる会員・組合員企業
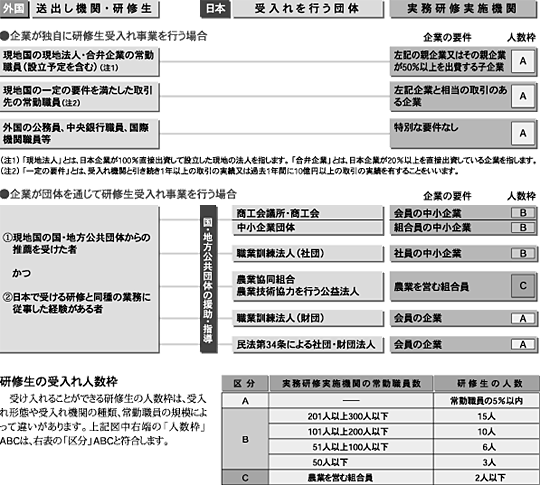
2.技能実習制度の具体的な仕組み
●技能実習生要件
次の条件をすべて満たす者です。
| ① |
技能実習を実施できる職種・作業について研修を修了した者 |
| ② |
技能実習修了後母国に帰り、我が国で修得した技術・技能を活かせる業務につく予定がある者 |
| ③ |
在留状況等からみて、技能実習制度の目的に沿った成果が期待できると認められる者 |
| ④ |
雇用契約に基づき技能実習を行い、さらに実践的な技術・技能を修得しようとする者 |
●技能実習生を受け入れることのできる機関
技能実習を実施できる機関は、次の全ての要件を満たす企業等です。
| ① |
技能実習内容が、研修活動と同一の種類の技術・技能等であること。 |
| ② |
技能実習が、研修活動が行われている受入れ企業等と同一のものが行うこと。 |
| ③ |
技能実習希望者と受入れ企業等との間に、日本人従業員と同等以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約が締結されること。 |
| ④ |
受入れ企業等が技能実習生用の宿泊施設を確保し、技能実習生の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講ずること。 |
| ⑤ |
技能実習実施機関又はその経営者若しくは管理者が過去3年間に外国人の研修・実習その他就労に係る不正行為を行ったことがないこと。 |
●技能実習を実施できる職種・作業
職業能力開発促進法に基づく技能検定の対象職種、又はJITCOが認定した技能評価システムによる職種で、2004年5月1日現在、62職種(113作業)があります。
このうち、国の技能検定による評価システムが51職種79作業、JITCO認定による評価システムが11職種34作業あり、農業、建設業、製造業等の産業分野に及んでいます。
●滞在期間
| ① |
研修と技能実習の期間の合計は、最長3年となっています。 |
| ② |
技能実習期間は、研修期間のおおむね1.5倍以内で認められます。ただし、研修期間が9ヶ月を超える場合は、この限りではありません。 |
| ③ |
研修期間が比較的短いもの(6ヶ月未満)は、技能実習は認められません。 |
●研修から技能実習への移行評価
技能実習への移行が認められるには、次の3つの評価をすべてクリアしなければなりません。
| ① |
研修成果の評価
全研修期間の6分の5程度を経過した時点で、国の技能検定、又はJITCOが認定した機関の試験を活用した評価システムにより、研修生が一定水準(国の技能検定基礎2級相当)以上の技術・技能を修得していると認められること。 |
| ② |
在留状況の評価
研修状況・生活状況が良好であると認められること。 |
| ③ |
技能実習計画の評価
研修生受入れ企業等から提出された技能実習計画が、研修成果を踏まえた適正なものであると認められること。 |
●技能実習実施機関の責務
技能実習生は、受入れ企業との雇用関係の下に報酬を受けるものであり、労働基準法上の「労働者」に該当することから、通常の労働者と同様、労働関係法令、労働・社会保険関係法令等が適用されます。受入れ企業はこれを遵守しなければなりません。
●技能実習生向け労働条件の通知書の交付
受入れ企業等は、トラブルを未然に防止し、適切な処遇を行うために、技能実習生に対し、実習内容、労働時間、賃金等に関する処遇について文書で通知しなければなりません。この文書は、労働契約書又は各国語版「外国人労働条件通知書」で行ってください。
●労働時間の取扱い
技能実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間、1週40時間の原則が適用されます。これを超えて受入れ企業等が技能実習生に、時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、一定の手続きが必要であり、かつ、時間外割増賃金等の支払いが必要となります。
●賃金の適正な支払い
賃金は、技能実習生の実習を通じた労働の提供に対する対価として、受入れ企業等が技能実習生に支払わなければなりません。この賃金は、労働基準法に基づき、技能実習生本人に直接、通貨で全額、毎月一定期日に支給しなければなりません。口座払いとするためには、本人の同意が必要です。通帳・印鑑・キャッシュカードは、本人に保管させてください。
なお、税金、社会保険等の法定控除以外の控除、例えば食費の控除を行う場合には、労使協定の締結が必要です。
また、送出し管理費は、賃金とは性質が異なり、送出し機関の適正選抜、派遣前教育、健康診断等に要する経費の全部又は一部を受入れ機関が援助するものです。受入れ機関と送出し機関は、送出し管理費と賃金を明確に区分し、賃金から送出し管理費を徴収しないようにしてください。送出し管理費をいくらにするかは、研修の場合と同様、送出し機関が行う業務内容を勘案し、受入れ機関と送出し機関で十分相談して決定してください。
●技能実習生のその他の処遇
技能実習生は労働者であり、業務上の事故や疾病が発生した場合、国の労災補償が受けられます。また、業務外の事故や疾病には、国の健康保険が適用となります。いずれも受入れ企業等は国の社会保険や労働保険に加入しなければなりませんので、ご留意ください。(保険料は、労災保険のみ受入れ企業等の負担で、他の国の保険は労使折半で負担です)
外国人研修生・実習生受け入れ
「縫製・紡績運転の技術移転」で研修生受入れ組合員企業の活性化、国際貢献を図る
当組合は、平成10年度から研修生の受け入れを開始し、現在では「婦人子供服製造」「紳士服製造」「紡績運転」に関して技術等の中国への移転を図って事業を実施している。また、同時に友好交流も深まってきている
■研修生を受け入れた背景とその経過について
 |
アパレル製品の製造の技能実習を
行っている研修生。
(長野アルプス(株)) |
当組合は、平成9年12月に長野県内の縫製業の6社が、不況の製造業界の中にあって情報、ノウハウの共有、研究等により現状の打開を図り、共存共栄していく目的で設立された。
中国の青壮年労働者を研修生として受け入れて、日本での縫製及び紡績運転の技術、技能、知識等を習得させ、研修生が帰国後に習得した技能を発揮することにより母国の産業発展に尽くすことが、国際貢献の一翼の担い手となり、当組合の発展に通じると思われ、実施してきている。同業者の新潟県長岡市の県央ファッション工業協同組合の紹介で「中国黒龍江省四達対外貿易公司」の送り出しにより、平成10年12月に第1期生18人を受け入れた。その後、平成13年からは中国国営企業「黒龍江省糧油食品進出口(集団)公司」から研修生を受け入れ、技術等の研修を実施してきており、現在まで受入総人数138人に至っている。第2次受入機関である組合員数は、現在13企業に増加し、組合事業を行っている。
■送り出し機関との係わり方について
「中国黒龍江省四達対外貿易公司」および「黒龍江省糧油食品進出口(集団)公司」の送り出し機関との事業合作関係で、中国の産業に寄与できる人材の育成に相互協力をしてきた。各組合員企業は、送り出し機関に年2回の研修生を受け入れる際に面接を行うため訪問している。送り出し機関の日本語、日本の風習等の教育は良くなり、レベル向上につながっている。
 |
| 清沢鈴幸理事長 |
|
我々日本人のものの考え方と外国の人のものの考え方の違いから、「はっきりとものを言う」「契約をきちんとする」ことが肝要である。
研修生に対する送り出し機関の教育レベルの問題、健康把握の問題等がこれから解決しなければならない課題となってきている。 |
|
■研修生の受け入れ後の経過について
縫製業の中小企業が国内生産をしている理由は、海外進出により現地工場で製造し、輸入した方がコスト面では有利であるが、期間短縮がされているとはいえ製造から販売までの調達リードタイムは国内生産の方が短縮されること、季節の変わり目やロットの小さな商品等は、売れるものを、売れるときに、売れるだけつくるための対応が可能となるからである。また消費者志向が低価格商品と高級品の二極化している中で、多品種少量生産に向く高級品は国内で生産する傾向にある。
これらの国内の中小企業が研修生を受け入れることにより、縫製業等が若年層の雇用が確保しにくい中で、企業の従業員構成のバランスから研修生等を受け入れることが企業の活性化にもつながってきている。
中国東北地方のハルピンでは、アパレル加工業は丸あげ(1人で一着を制作する)といった方式で製造しているが、日本ではグループ、ラインで製造を行っている。ライン、グループの方が製造スピード、品質等が良くなり、ポイントとなる部分の技能がアップするからである。研修生、技能実習生に、実習を通していくつもの工程を経験させ、いろんな部分の技能をアップさせることにより、研修生が中国に戻り、丸あげで製造を行う場合のレベルアップにつながっているといえる。
■受け入れての問題点と対応について
研修生、技能実習生の仕事に対する意欲は非常に高い。一生懸命行っている。但し、3年目になると帰国が近づくせいか、その意欲も低下する傾向がみられる。最後まで意欲的に行ってもらうことが、この事業の評価につながってくると思う。また、日本と中国との物価の違いにより、倹約、節約する研修生が体調を崩すケースも考えられる。健康管理面で細心の注意を払うことがこれからの課題の一つである。
民俗性、国民性の違いがあり、日本との違いで良い面と悪い面がみられる。当組合では、日本に来て10年以上経ち中国語の通訳として常勤している女性職員を雇用しているのも強みである。通訳だけでなく、研修生の生活指導も行ってもらっている。当組合の場合は100%女性の研修生なので、女性同志の話し易さもある。送り出し機関との交渉時も同行し、活躍してもらっている。
■外国人研修生受入団体連絡協議会について
団体同士の連携を図れるので必要であると思う。組合、企業等の受入経験に基づき、いろいろと情報交換ができるので、トラブル等が未然に防ぐことが可能になるのではないだろうか。


| ■名称 |
 |
長野ファッション工業協同組合 |
| ■組合事務局 |
|
長野市高田1094番地1 |
| ■連絡先 |
|
TEL・FAX 026-224-3277 |
| ■設立 |
|
平成9年12月24日 |
| ■組合員 |
|
| 長野アルプス(株) |
 |
(有)シガ・ファッション |
 |
(株)日昇堂 |
| 更級被服(株) |
|
大田縫製(有) |
|
(株)スリーヤーン |
| (有)長野クリエートアパレル |
|
母袋産業(株) |
| (有)ヒジリヤーン |
|
ビエラジャパン(株) |
|
(有)ラジェル |
| エーワン、クロース |
|
モンテローザ |
|
以上13名 |
|
|
| 長野県外国人研修生受入団体連絡協議会が発足しました
中小企業団体が第一次受入れ機関として外国人研修生・技能実習生を受入れる制度が発足してから10年が経過し、その間、多くの若年者が長野県内の各企業においても研修・技能実習を受け、帰国後それぞれの国で活躍しています。
しかしながら、外国人である研修生・技能実習生に対し、法的権利、人権の保障が十分であるのか、技術・技能の移転が十分になされているか等々の指摘があります。
これらの課題に対処するために10月26日に国の外国人受入れ制度を利用して研修生・実習生を受入れている中小企業協同組合等が受入れ事業に関しての情報交換、交流促進等を目的に連絡協議会を設立しました。
設立総会では、発起人を代表して二十一世紀会事業協同組合の百瀬理事長より、協議会設立趣旨について述べられ、外国人研修生受入制度の運営に関して一部の受入団体や受入企業が法律、制度の趣旨に外れた行為をしている例が見られるので、これらの問題解決や受入団体間相互に連携をとり、事業目的に合致するよう挨拶がなされた。
百瀬発起人が議長に就任し、会則、16年度事業計画等の決定後、役員選出が行われ、次の方々が就任いたしました。
役員名簿
| 役職名 |
氏名 |
組合名 |
| 会長 |
百瀬 昭 |
二十一世紀会事業協同組合 |
| 副会長 |
清沢 鈴幸 |
長野ファッション工業協同組合 |
| 理事 |
花村 薫 |
明科工場団地協同組合 |
| 監事 |
松橋 公 |
長野シークス事業協同組合 |
|
|
平成16年度事業計画書
| 自: |
平成16年10月26日 |
| 至: |
平成17年3月31日 |
|
Ⅰ.基本方針
わが国経済のグローバル化・ボーダレス化に伴い、組合が実施する「外国人研修生受入事業」の重要性はますます大きくなってきているが、全国的には一部組合において不正行為が発覚するなど、運用面において様々な問題が発生している。
本事業の本来の目的である開発途上国の人材育成協力という視点にたち、研修生の秩序だった受入、研修生・技能実習生の技能向上など事業の適正な運営を推進していく上での課題を明確にし、問題解決に向けた取り組みを実施する。
組合の発展は組合員企業の発展があってこそとの視点にたち、組合員企業のニーズを探り、組合の果たすべき役割について協議を行う。
Ⅱ.実施事業
| 1 |
 |
情報交換会の開催
外国人研修生を受け入れるにあたり障害となる問題や、適正な事業運営を行うために必要な情報の交換を行う。 |
| 2 |
|
研修会の開催
次年度より実施する。 |
| 3 |
|
その他の事業
会長が必要と認める事業について随時実施する。
また、新規会員の増強に努める。 |
|
国際研修協力機構 長野駐在事務所
主任駐在員 塚田昌之 |
グローバル化の進行
グローバルな企業競争社会が急速に進行しています。特に中国や東南アジアを中心とした開発途上国からの追い上げ、企業の進展、取引等の影響は、国内企業経営の中で大きな課題となっているのではないでしょうか。この課題解決の第一歩は日本人とは、言語、文化、習慣、価値観等の異なる外国人を理解することから始まりますが、これには多くの労苦と根気が伴います。
中小企業が行う研修・技能実習制度
外国人研修生の受入れ事業は、昭和40年代頃までは大企業が中心で現地法人、合弁企業、取引関係のある企業の社員を招聘し技能・技術、知識等の移転を進めていましたが、40年代の高度成長ピーク時から中小企業の海外進出や国際貢献についてずいぶん議論されました。こうした中で誕生したのが「中小企業団体監理型」の事業として行う研修生・技能実習生受入れ事業です。
多様な事業効果
この事業の本来の目的は、中小企業団体の監理のもとで個々の企業へ研修生を委託し、研修を実施し研修が終了した後、一定の要件を満した事業所・研修生については、更に雇用労働者として日本人の労働者と同一の条件で働きながら技能や技術を身につける(技能実習)制度で、この間に身につけた技能・技術、知識等を母国へ持ち帰り母国の発展に貢献することにありますが、実際に受入れている事業所の状況を見ると様々な波及効果が出ています。
主なものをあげてみますと
| 1 |
 |
異文化と交流によるグローバル意識の向上 |
| 2 |
|
将来に向けて海外取引の拠点作りや情報等の的確な掌握 |
| 3 |
|
研修生・技能実習生への指導体制の確立とそれに伴う職場の活性化 |
| 4 |
|
社内研修制度の見直しや制度の確立・改善効果 |
| 5 |
|
実務研修(雇用労働)による作業の効率化 など |
これらの中で生活習慣などの違いでトラブルが生じ対応に苦労をしている事例も散見されますが、お互いに正しく理解し合うことによって解決できるケースがほとんどです。
長野県での受入れの実態と特長
過去5年間の受け入れ状況は、表のとおりで中国からの受入れを中心に更に増加するものと思っています。
実際に受入れるとなると様々な不安がありますが、長野県内に設立されているほとんどの団体では、まず研修計画や受入れ枠を設定しますが、その後実際に受入れる研修生の選抜方法は、受入れ企業の事業主と受入れ団体が現地に出向いて、送出し団体と三者が一堂に会して選考する方式をとっています。
この場合受入れ事業所独自に作成された適性検査、能力テスト、体力テストや面接等を実施し、受入れ後の研修や技能実習が効率的に出来る人材の確保に努めています。
この方式は今日まで受入れ団体の経験の中から編み出されたもので、この方式の導入によって受入団体・企業が行う研修や雇用管理面でずいぶん改善が図られました。
おわりに
技能実習制度が出来て10年経過しました。この間に国際間の労働力移動や技術・技能も急激に変化し、現行制度も新たな対応が指摘されるなど論議されていますが、国際的にも高く評価されているこの研修・技能実習制度は一層充実するものと思っています。
グローバル化が更に進む中でまずこの制度の活用についてご検討ください。国際研修協力機構ではこの制度をサポートし様々な相談に応じています。
また、国際研修協力機構としては、受入企業がこの制度を活用し事業活動の国際化、効率化を進められ、更に目的である国際的な人材育成のために、この度長野県中小企業団体中央会傘下の協同組合を中心に設立された長野県外国人研修生受入団体連絡協議会(事務局 長野県中小企業団体中央会)と連携を密にとり事業の充実を図っていきたいと思います。
| 国 名 |
12年10月末 |
13年9月末 |
14年9月末 |
15年9月末 |
16年9月末 |
| インドネシア |
573 |
615 |
704 |
539 |
452 |
| 中 国 |
85 |
140 |
348 |
401 |
616 |
| タイ |
11 |
12 |
21 |
10 |
9 |
| ベトナム |
4 |
0 |
3 |
19 |
7 |
| スリランカ |
2 |
7 |
4 |
3 |
0 |
| ミャンマー |
0 |
3 |
2 |
6 |
0 |
| フィリピン |
0 |
2 |
8 |
0 |
8 |
| モンゴル |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
| 合 計 |
675 |
779 |
1,090 |
978 |
1,094 |

資料:(財)国際研修協力機構 長野駐在事務所 |